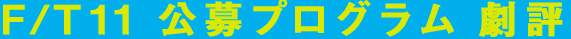役者という使者の祝祭 (『エンジェルス・イン・アメリカ』)
<小澤英実>
トニー・クシュナーの『エンジェルス・イン・アメリカ』(以下AIAと表記)は、エイズパニックがアメリカ本土を席巻した90年代初頭に書かれたアメリカ現代演劇の金字塔的戯曲である。アメリカ社会を構築する三大要素とされる「人種・階級・ジェンダー」に、「政治と宗教とセクシュアリティ」という3項を導入することで、共同体幻想を粉砕するようなアメリカ国家のマトリクスを観客にまざまざと見せつける。それは多民族国家アメリカの病理と救済の物語であり、ひとりのユダヤ系アメリカ人が、アメリカという内なる他者を理解しようとして書いた、途方もなく野心的な戯曲であり、第一部・第二部を通しで上演すれば、ゆうに7時間におよぶ壮大なスケールの叙事演劇である。1
80年代アメリカの歴史・政治・宗教・文化の百科事典のようなこの作品を2011年の東京で上演するにあたり、演出の杉原邦生が取ったアプローチは、徹底した「リアリズム」――戯曲のテクストをできるかぎり忠実に舞台上に再現しようとすること――だった。ブレヒトを師と仰ぐクシュナーの意図を正確に汲み、天使が同時に生身の人間であることや、ジャージを着た役者たちが場面転換を行いこれが虚構であることを絶えず喚起することで――それらの指示はト書きに書かれているとおりだが、とはいえそれを忠実かつ的確に演出することによって――舞台上に異化効果を生むことに成功していた。今回の上演において、杉原邦生とKUNIOのキャスト、スタッフたちが、これほど真摯に戯曲に寄り添い、演劇という一語で括られるさまざまなベクトルの力をひとつに結集し、文字のなかに捕らわれた天使をみごとに羽ばたかせたことに対して、心から拍手を送りたい。だが、このアプローチを採用したことによって、得たものと失われたものの双方があることもまた事実だ。
今回のKUNIO版『AIA』の大きな功績は、「演劇だけに語りうる物語のもつ力」を見せつけたことにある。それは劇作家であるクシュナーの戯曲そのものに内在する力であり、それを最大限に引き出したのがこの上演であった。クシュナーは自分の劇作術について次のように言っている。「僕の書く芝居は、実際に舞台に乗って観客がそれを観ているときに、「あっ、これは書かれたものを観ているんだ」とどこかで意識してもらえるようなものでありたい。そして逆に同じ芝居を今度は本で読んでいるときには、この本の中に書かれていることは役者(人間)が本当に舞台に立たなければ完全には実現しないものもあるんだというふうに把握してほしい。(略)僕の戯曲は小説でもないし、詩と音楽のスコアとも違う、もちろん単なる台詞の羅列だけでもない、そういうものすべて含めた作品でありたい」。2 ここで重要なのは、劇作家が戯曲の言葉と上演を等価に、互いに含まれ合い、どちらが欠けても不完全なものとして規定している点だ。クシュナーのスタンスは文学中心主義でも、ポストドラマ演劇でもない。そこから語られる物語は、演劇のみに語りうる物語なのである。
昨年の岸田國士賞における宮沢章夫の選評は、現在の日本演劇において、戯曲の言葉と上演の関係性を改めて問い直さなければならなくなっている状況がよく表れている。演劇における戯曲中心主義、文学主義が否定されてはや五十年近くが過ぎ、その超克の一貫としてパフォーマンスやポストドラマ演劇の隆盛がある現在、「上演」とはべつに「戯曲」の質を問うのはなぜなのかと宮沢は言う。「簡単に(いや、乱暴に)言ってしまえば、やはり演劇は「戯曲」だったからだ。「新しい演劇の仕組み(=ドラマツルギー)」はテキストのレベルでなければわからない。(略)「身体」か「言葉」かという二分法もどうでもよくなった。よく言われる「総合芸術」という言葉もひどく曖昧だ。さらに乱暴な言い方をすれば、「総合」だからなおさら要素が分散し劇の構造をはっきり把握することなどできなかった」3 。宮沢が述べるように、「やはり演劇は「戯曲」だったのだ」ということ、だが、そのためには戯曲の言葉が演劇のための言葉、演劇のための語りでなければいけないこと。そして、こうした宮沢の問題意識の傍らに置くべきなのが例えばこの戯曲であり、それを丁寧に再現することによって、ドラマ演劇のもつ力を改めて見せつけたこの上演だったといえるだろう。
だが、KUNIO版AIAをこのように言祝ぐ一方で、私自身の感想を正直に言えば、2004年のTPTの公演を観たときの体験を越えることはなかったという想いもどこかにある。TPT版では初めて上演を観たという衝撃や感動もあったし、ベニサン・ピットのような天井の高く広い空間での上演と比べるのは意味のないことかもしれない。今回の会場である自由学園明日館講堂のなかに一大スペクタクルを立ち上げたことは称賛してあまりあるが、とはいえ、もとはキリスト教の教えに基づく学校施設であり、結婚式にも使われることの多いこの講堂の力を十全に活かしていたとは言い難い。KUNIO版AIAを考えるうえで重要なポイントは、舞台と客席の位置関係にあると思う。客席は長方形の会場の長辺の両サイドから舞台を挟む形で配置され、それにより、劇中のほとんどの時間、舞台上で起きている出来事、登場人物たちの行為を真横から眼差すことになる。この配置にすることで、観客が上演の成立の欠くことの出来ない要素として上演の内部に関わる情況を生み出したかったのだろうという意図は感じられる。だが、それによって観客は、登場人物たちに対峙するのでもなく、天使が自分達にむかってせり出してくる体験をすることもない。結果的に、それはどこか映画的で、あるいはあたかも流れていく車窓の景色のように、そこで起きている出来事を覗き見ているような感覚に近くなる。やがては観客が傍観者のような、没入と批評意識が同時に存在することで生まれるブレヒト的な異化ではなく、没入を阻害する距離のみが生まれてしまったように思える。
もうひとつのポイントは、アメリカ特有の文脈や事象を観客に理解させようとすることに重きが置かれていなかったことについてだろう。この戯曲を書いたクシュナーのねらいは、登場人物たちのドラマの背後からアメリカの国民国家を見守るベンヤミンの歴史の天使を召還することにあったわけだが、上演における杉原の関心はそこにもなかったように思える。というのも杉原は、文化翻訳たる上演に際して、テクストの「直訳」――つまり台詞の言葉をそのまま発話するだけで、理解の補助となるような特別な演出はしないこと――という処理を選択したが、もし観客に文脈への参与を求めるならば、その翻訳=演出は「直訳」では済まないからだ。その代わり、今回の杉原演出では、TPT版でカットされた部分も含めてすべてを忠実に上演したことが眼目になっている。その部分、それは奇しくも、第二部の終盤、天使たちがチェルノブイリの事故を報じるラジオを聞き入るくだりを含んでいる。クシュナーが本作で描いた黙示録的世界観は、3.11以降の日本にとってはひどく既視感がある。90年代のアメリカを襲ったエイズ危機――目に見えない死に至るウィルスが拡散する恐怖と脅威――に、目に見えない放射能が拡散する2011年の日本を重ね合わせ、人類の希望を謳いあげること。そこに今年、第二部を合わせた上演を行った意図があったに違いない。だが、そのエイズウィルスや天使をめぐる可視化と不可視化の物語を3.11以降の日本の物語に接続するために、もう少し積極的な演出=コミットがあってもよかったのではないか。その一方で、杉原の演出である第二部のエピローグ、セントラルパークの象徴であるベセスダ噴水の天使像の前に腰掛けた四人の場面を、人形劇に仕立てた意図はよく摑めなかった。語り得ぬ出来事や「以降」の事象を語るためには、「以前」の出来事を語り直すことが何よりも力をもつ。だが、アメリカ的な要素をフィルター抜きに舞台に乗せたことで、戯曲のもつ豊穣なテクストが、結果的に日本の小劇場の文脈へと矮小化されてしまうという点はあったように思う。
では、今回の杉原版AIAの最大の功績はなんだったのか。それは、役者たちの演技が上演を支え、役者たちの存在に最大の焦点が当たる上演になったことだと私は思う。第一部のみを上演した2009年のKUNIO06 から、第二部を含めた今年9月のKYOTO EXPERIMENTを踏まえた役者たちの演技には確かな自信が感じられ、信頼して観ることができた。全員が発声や滑舌がよく、技術を持っているというわけではない。そうではなく、彼らの演技と集中力、彼らの全身から滴り落ちる汗、発散される凝縮した熱のようなものが、少し底冷えのする講堂を照射していたのだ。彼らは、戯曲を忠実に再現しようとして幾度となく全裸になる。そこには、エイズウィルスに蝕まれた瀕死の肉体という虚構を演じる、役者たちの健康な生身の肉体がある。そこから放たれる声や熱が観客を包み込む。9時間にわたって観客が見続けたのは、ただ彼らの身体のみである。この上演がこんなにも素晴らしかったのは、そこで役者たちが生きていたからだ。彼らが役を生きているだけでなく、それと同時に、生身の役者として生きていたからである。それこそクシュナーが書き記した演劇の呪文であり、それを見事に立ち上げたのがこの上演だった。こうした演劇だけがもつ力を正しく理解し、その効用を心から信じて演劇に身を捧げている若い演出家の存在が、何よりも頼もしく感じられる舞台だった。
1 日本では1994年に銀座セゾン劇場で初演(第一部のみ)、2004年と2007年にTPTが通し上演(ロバート・アッカーマン演出)を行ったほか、アメリカで上映されたテレビドラマ版も存在するため、本稿では戯曲についての詳述は割愛する。クシュナーと日本の小劇場演劇について言及した他の拙考に「めぐり合う身体たち――『生きてるものはいないのか』と『ゴースト・ユース』の実践」『舞台芸術13』がある。
2 「作者は語る」『エンジェルス・イン・アメリカ』、文藝春秋、1994年、239頁。
3 宮沢章夫「いま書かれるべき、戯曲としての上演台本」<http://www.hakusuisha.co.jp/kishida/review55.php>
- KUNIO
- 2012年01月06日