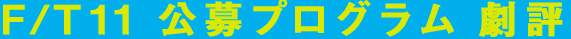ユーモアあふれるハッタリに、敢えて物申す (『ノーション:ダンス・フィクション』)
<高橋彩子>
フェスティバル/トーキョーのウェブサイトで「人間の筋肉の動きをデジタルで記憶させることにより、ダンス界のアイコンともいえるピナ・バウシュや土方巽などの振りを再現するデモンストレーション・パフォーマンス」「最先端のテクノロジーと身体言語としてのダンスとの化学反応」という触れ込みだった『ノーション・ダンス・フィクション』。筆者が事前に抱いた漠たるイメージは、舞台を観るうち、裏切られていった。
電気を巡るプレゼンテーションと実演の効果
舞台上にはスクリーンと、コードを多数つなげたパソコンが置かれている。やがて、チョイ・カファイと、シディ・ラルビ・シェルカウイのもとでも踊ったダンサーのスベンソン・ウルリカ・キンが、通訳の近藤強を伴って登場する。こうして、カファイがトークで主導する、スクリーンとキンのダンスを使ったプレゼンテーションが始まる。
彼はまず18~19世紀の科学者たち――電気伝導を発見したスティーヴン・グレイ、身体に電気を通すと筋肉が動くことを発見したルイージ・ガルヴァーニ、その甥で死体に電気を流して動かそうとしたジョヴァンニ・アルディーニ、顔の表情の実験をしたデュシェンヌ・ド・ブーローニュなど、次に20世紀に飛び、90年代のテクノロジーを駆使したアーティストたち――ステラーク、アルトゥーア・エルセナー、真鍋大度らのアートを、順次解説していく。
これらの紹介のあと、カファイは「筋肉を刺激することで動きを作り出すことができる」「3Dのアニメーションを作る時と同じように、身体にセンサーをつけて映像と同様に動かし、その際の筋肉の情報をデータベース化した」「歳月が過ぎてもこのデータを取り出して電流を使って身体に移植すれば、どんな振付でも再現できる」とこともなげに述べる。そして実際にキンの身体に、舞踊史上に残るさまざまな振付家の作品の情報を流し、キンを"自動的に"踊らせ、同時にキンの背後のスクリーンに、その作品の映像も流す。このデモンストレーションは、いかにも胡散臭い。そもそも脳からの指令によって複雑に動く筋肉を、外的な刺激で全てコントロールできるのか? 研究すべきは筋肉よりも脳ではないのか? もっとも、カファイが参照する舞踊家・振付家の脳の多くは現存しないから、そこに手を出せないのは致し方ないのだけれども。
ともあれダンス映像が流れるスクリーンの前方で、キンの身体は電流によって、映像と同じ動きを強いられる......はずである。だが、彼女の動き方にしろ止まり方にしろ、電流によって筋肉が自動的に動いているようには思えない。そもそもその身体には、電流を流すのに使うはずのコードすら接続されているように見えない。途中、スクリーンの映像が延々と同じ箇所で短い再生を繰り返し、キンの動きも同様のトラブルに見舞われるという"システムエラー"も起きるが、これもまた作り事だ。なぜならキンの動きは、映像そのものからではなく、あくまで映像とともに動いた人物を使って採取したデータに由来するはずで、ここで映像と電気の刺激が同じような故障の症状を見せるのは不自然である。カファイはさらに、振付家3人の動きをミックスした情報をキンの身体に流す。だが、筋肉レベルでそのような違う情報を流したら、身体は深刻なダメージを受けかねないだろう。
そんなわけで観客は、初めはテクノロジーを駆使するかに思われたこのプロジェクトが、ジョークのようなもの、いわばフェイクだと了解し始める。
しかし、観る者はまだ、どこかで信じている――カファイが実際にやっているかはともかく、筋肉を記録して再現すること自体は、理論上、必ずしも不可能とは言えない事柄なのではないか、と。
見かけ上の動き/動きの本質を巡るアイロニー
舞踊にたずさわる者にとって、舞踊譜の確立は長らく大きな課題だった。ベネッシュノーテーションやラバノーテーションなどは今も有効なものとして知られているし、ビデオの登場によって、モーションキャプチャーの技術も発達した。カファイが試みた筋肉の動きの記録も実際、ある程度まで舞踊のデータベース化に貢献するものかもしれない。こうしたデータベース化を支える大きなモチヴェーションとなっているのが、「あの振付家・踊り手のダンスを再現したい・踊りたい・解明したい・この目で観たい」などといった舞踊家や舞踊研究家や観客の夢・欲望だ。そして、カファイのプレゼンテーションは、「巨人の星」で言うところの"大リーグボール養成ギプス"のようなもの、つまり、ある種のテクノロジー神話に依拠してその実現を目指すものと言える。
だからこそ、野暮を承知で敢えてこの夢に則りながら、マジメにこの舞台について考えてみたい。カファイの説明によれば、ここでは映像からの動きを、別の人間の身体を通してデータ化し、それを、さらに別の人物(ここではキン)の身体に電流で移植することができると言う。それを信じるとして、果たしてそれはオリジナルのダンスを再現していると言えるのか? 残念ながら、否だ。
ぱっと見、同じポーズを取っても、使っている筋肉が同じとは限らない。外側の筋肉を使ってそれらしい動きができていても、実は内側の筋肉を使わなかったことで、振付の意図する緊張感やエネルギーが損なわれるケースも考えられるのだ。振付家やダンサーは、そうした部分を日々、研究し、鍛錬している。
カファイが映像を用いてデータを作ったとする以上、アングルや身体部位の都合で映像に写らない部分は、たとえ動きを作る上で決定的な意味をもっていても、見落とされる可能性がある。また、映像に写る一人の人物だけからデータを取るこの手法は、音や光、共演者同士の相互作用などがもたらす効果も取りこぼしている。すなわち、この方法は、動きのパターンなどを分析・記述した上で、上演する際の諸注意をも言葉で指示しているような舞踊譜よりも、本来の振付から乖離する可能性が高いとすら言えるだろう。
実際、ダンス映像の横で実演するキンの姿は、映像と概ね同じであるにもかかわらず、映像にあるダンスの魅力を余すところなく再現しているとは誰も感じないはずだ。このことは逆説的に、舞踊というものは何なのかを浮き彫りにしてくれる。ダンスの本質は必ずしも、外形上の動きの類似によって表現されはしない。むしろ、舞台芸術の神秘とは、同じ仕草をしているようでいて、どうしてここまで変わるのかというくらい、伝わる印象が違う点にこそある。残念なことに、大リーガーの筋肉の動きを記録し、大リーグ養成ギプスを作っても、現実には誰もが大リーガーの筋肉をもつことはできないし、大リーガーになれるわけでもない。舞踊史に残るビッグネームたちの動きをデータベース化することで、一見すると脱神話化を果たそうとしているカファイの方法論は、逆説的に、ビッグネームがビッグネームたるゆえんを照射する。
勿論、カファイは、そんなことは端から承知でこのフィクションを作ったのだろう。ここでしかし、プロのダンサーであるキンの存在が、事態をよりいっそう複雑化する。映像上映とキンの身体によるデモンストレーションが一通り済むと、カファイはキンに、もう電流は流さないから、自分の記憶のままで踊ってみるようにと指示しする。キンが踊るソロで、『ノーション・ダンス・フィクション』は終わる。このソロはといえば、筋肉に電流を流したという「フィクション」の影響下にあるかどうか、はなはだ曖昧だった。似ていると言えば似ているが、それまでのデモンストレーションと同じ動作ではない。どうせなら、それまでに流した映像の動きをめまぐるしくすべて再現してみる、くらいの仕掛けを施してもよかったのではないか。あるいは逆に、まったく吹っ切れた踊りを見せてもいい。ことによると、どちらでもないことで、作品を開かれたもの・広がりのあるものにする意図があったのかもしれないが、それが成功しているようには感じられなかった。せっかく準備したフェイクの世界が、壊れてしまいかねないようにも見えた。
思い起こせば、開幕後ほどなく、電流を流すより前、カファイがさりげなく披露した舞踏の真似は、その後のどのダンスよりもサマになっていた。見よう見まねで行ったカファイの動きが一番オリジナルに近く、電流まで流してダンサーのキンに移植した動きが、オリジナルから遠ざかったコピーとなり、最後にはそのコピーからも離れるという皮肉な現象が起きたかっこうだ。
そう考えると、もう少し、彼女の身体を生かしてほしかった気もする。理論上、筋肉の動きをコピーできるということになっているのだから、キン自身が踊るキンのオリジナルのダンスこそ、コピーのソースとして真っ当だったはずだ。例えばそれをカファイに移植するといったアプローチも可能だった。舞踊史上に残るダンスのコピーという大ハッタリの前には弱いにしても......。
不満はほかにもある。例えば、あれだけ舞踊史に残る映像を用いながら、なぜウィリアム・フォーサイスに言及しなかったのか。彼こそ、テクノロジーを駆使した舞踊のデータベース化にいち早く着手した振付家だ。プロのダンサーであるキンを起用するメリットは、ここにも生まれたはずである。理由は不明ながら、その引用がなかったことが惜しまれてならない。
「ダンス・フィクション」なのだから全て冗談としておおらかに観ればいい、という考え方もできるだろう。事実、ここでは敢えて難癖をつけた筆者も、上演中はかなり楽しんだというのが正直なところだ。また、通訳の近藤が、カファイの言葉を逐語訳するだけでなく、「~だそうです」「そんなわけないですよね?」などと観客に語りかけるような言葉遣いでもって舞台と客席の橋渡しをした結果、飄々とおかしなことを言っているカファイの人物像がよく伝わっていたことにも触れておきたい。
しかしながら、一度鑑賞を終えてみると、もう一ひねりほしかったという思いを禁じ得ないのだ。結局のところ、こうしたドキュメンタリー仕立ての作品は往々にして、周到かつ綿密に積み上げられたフィクションの力に依存しているからである。
- チョイ・カファイ
- 2011年12月06日