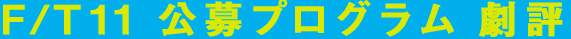匿名的なものたちの饗宴――「引用」の問題を中心に (『常夏』)
<江口正登>
ロロについての判断を下すことには、独特の困難がつきまとう。それは彼らの作品が、ある種の共感を、したがって同様にそれを裏返した反感を強く喚起する類のものであると思われるからである。共感や反感は、作品に対する我々の態度を根底的に動機づけるという意味で、決して意義のないものではないのは確かだが、批評にとってはしばしば躓きの石である。
以上のような判断から、本稿では、ひとまずレジュメ的なスタイルを採用することとする。衒いのないレジュメとして、『常夏』の構造と、そこに観られるロロの作風・手法・特徴を整理し、これに対する基本的な批評的理解を確保することをまず第一の課題とし、その上で、より批判的な角度からいくつかのコメントを行いたい。
というわけで、まずはストレートに、作品の要約記述から。
『常夏』は、from風呂美という少女が語る物語として提示される。彼女は、「いつかの夏」にバスタブで生まれた少女であり、「生後五秒」である。したがって彼女によって語られる『常夏』の物語は、五秒間のあいだに彼女が見たものであるということになる。
五秒間のあいだに風呂美が見た物語とはいかなるものであるか。彼女自身が繰り返し念を押すように、それは夏の出来事である――あるいは、そうした出来事の一つ一つこそが夏をそれとして定義する――ということだけは明確であるものの、それ以外のことを適切に要約するのは難しい。とりあえず登場人物を基準に記述すれば、幾度となく出会いと別れを繰り返す少女と少年(の分身たち)(釘宮左とおさむ達)、ある女の素行調査を依頼された私立探偵とその助手(鉄マリオと小窓小道)、彼らの調査対象である女と、彼女によってバスタブに軟禁されている弟(ホノル流貴子江とホノル流山火事)、地球壊滅を企みつつも気弱な男(ザリガニ?)とその凶暴な部下(セバスチャンとブロッケン・ハンマー)、と、ひとまず四つのグループに整理することができる。これらが、絡まりあいながら進行し、最終的に、モラトリアム的にパーマネントな夏の継続が確認され、生後五秒を経て恋に落ちた風呂美の歓喜に満ちたマイクパフォーマンスによって終幕へと到る。――ごくごく大雑把にではあるが、物語内容はひとまずこのように要約できるだろう。
作品の主要な特徴は次のようなものである。(1)サブカルチャーへの膨大な参照、(2)「ボーイ・ミーツ・ガール」と要約されるドラマトゥルギーの全面的な適用による、プロット上の諸要素の連結・分離の自在さ1、(3)マンガ的にデフォルメされたキャラクターと、それに応じてデフォルメされた台詞が帯びる詩的な強度、(4)大道具・小道具の――写実性とは別次元の――マテリアリティに対する固執から成り立つ、ガジェットに満ちた舞台空間の運動性。さらに、殺陣の場面や夏祭りの神輿の場面など、スペクタクル的な場面の演出の巧みさも(5)として加えてよいかもしれない。
これらの特徴は、様々な仕方で評価することが可能と思われるが、ごく大きな枠組みに則るならば、近代的なドラマトゥルギーや人物造形、またそれに則った台詞と演技の文体、セノグラフィのあり方を相対化するもの、というのが一般的な位置づけ方であるだろう。あるいは、より微視的な視座をとって、近年の小劇場の展開の中で考えてみるならば、そのセノグラフィは、チェルフィッチュ以降の抽象的な形式性やミニマリスティックな美意識が支配的となっていく傾向の中で、具体的なモノの力を探究したものとして見ることができるし、キャラクターのマンガ性ということも、これまたチェルフィッチュ以降の、人物の内面及び世界や他者との関係の取り方の双方に注がれる、現象学的な視線の精緻化ということとは全く別のタイプのナラティヴを可能にするものとして捉えられるであろう。
しかしながら、こうしたロロのスタイルは同時に、多くの批判を喚起しうるものでもある。分けても、劇作・演出を務める三浦直之の引用癖、とりわけサブカルチャーに対する引用癖は――この作家の特徴として肯定的に言及されることもまた頻繁にあるのだが――批判に晒されることが多いように思われる。そうした批判は基本的に、「元ネタが分からないと楽しめない」ということに集約される。この批判は、すなわちロロの作品が「元ネタの共有を不当に前提している」ということ、したがってそうした「ネタの共有に基礎を置いている、またそれを可能にしてもいる、同質的な共同体に依拠していること」を含意している。つまりこうした批判は、「同質的な共感の共同体の内で戯れあっているだけであり、他者を欠き、閉鎖的」といった、ロロを含めた若い世代の演劇に対してしばしば向けられるステレオタイプな批判の一典型であるのだ。であるならば、この批判はそのステレオタイプとしての遍在性のゆえに、つまりそれ自体が「症候」の如きものとして、特別な検証に値するだろう。こうした判断に基づき、以下では、『常夏』におけるサブカルチャーの引用という手法の構造と機能について詳しく考えてみたい。
「元ネタが分からないから分からない」。ロロの作品に対してしばしばなされるこうした批判は果たして妥当なのであろうか。まず指摘されねばならないのは、何かを引用するということは、その引用元=原テクストに対する前もっての十全な理解を常に必要とするものではないということだ。
そもそも、原テクストに対する――歪曲的なそれも含めて――理解の深化や伝達に関わらない類の引用もありうるだろう。こうした引用においては、引用が引用であること、そこでなされている振舞いが何かの引用であるということそれ自体に意味が置かれている。そこで重要となるのは、原テクストにおける意味作用をそれがどのように変形・再配置したかということではなく、むしろ、その行為が、それが位置づけられる当のテクストにおける連辞的・範列的な構造の内で、いかなるアクセントやトーンを帯びたものとして作用するかである。これらは、いわば〈身振りとしての引用〉という風に呼ぶことができる。
さらに、仮に引用が、原テクストの意味の水準に関わるものであり、したがってそれに対する理解を要するものであった場合2にも、そうした必要な理解が引用の行為と同時に提供される、したがって前知識が必要とされない場合もあるだろう。
以上を踏まえた上で、それではロロにおける引用とはどのようなものか、具体的に、作品に基づいて見ていこう。『常夏』の作中で、明示的な引用の対象となっているといえるものは、ディズニー映画の『リトル・マーメイド』、細田守によるアニメ映画『時をかける少女』、そしてあだち充の漫画作品『H2』(あるいは『タッチ』)の三つであるだろう。この内、『リトル・マーメイド』の場面は、海底の空間を群舞的に表現するものであり、文字通り一つのスペクタクル=身振りとして受容しうるものである。したがって、これを楽しむために特段の前知識はもちろん不要である。
『時をかける少女』の場面も、作品に対する前提知識を強く要請するものではない。この場面を理解するのに必要な知識は、それが二人の恋人の別れの場面であるということぐらいであり、明らかに「見れば分かる」類のものである(映画内の場面が無言で演じられることは、むしろ必要以上なほどにそれを裏付けている)。この場面のポイントは、現実世界に属する貴子江がスクリーンの中へと闖入しそのプロットを書き換えてしまう(別れる運命にある二人を無理やり結びつけてしまう)ことにあるのであって、これは、『時かけ』という個別の作品に対する知識とは別に、映画という表象形式と現実世界との関係に関する一般的な知識があれば誰にでも理解できるものであるだろう(もちろん、『時かけ』を観て真琴と千昭を引き裂く運命の無情さにいたたまれない想いをした者であるほど、この場面に感情移入しうる、という構造はある。しかしながら、この場面がそうした水準にのみ依拠しているものではないことも明白である)。
そして、『H2』の場面。この場合も、一連の流れのポイントを理解するために特別な知識は不要である(あだち充が漫画家の名であることが分からなければ厳しいが、それは前後の文脈から分かるはずだ)。弟・山火事の現実の願望(甲子園に行きたい、野球部に入りたい)に対し、姉・貴子江は漫画(=表象)の再現で応えようとする(「あだち充みたいにいこう」)という転倒、しかしそうした転倒した再現であるはずのものが実質的な効果(「たそがれ」感)を発生させてしまうという更なる転倒、そしてこうした転倒の基礎にある現実から再現への移行を支える、笑いを誘うようななだらかさ。これらがこの場面のポイントであり、これもまた『H2』という作品に対する知識とは関係なく理解できるはずのものである3。
さらに、実のところ『時かけ』にせよ『H2』にせよ、実際に観たことはなくとも何となくその内容に関して想像がついてしまえることが重要である。『時かけ』における真琴と千昭の運命の成り行きも、『H2』における国見と古賀の煮え切らない関係とそこに介入する第三者(三善)という構図も、どこかで「聞いたような」ものであり、事実としてそれらを知らなくとも、「ああ、あるよね」と何となく了解してしまえる類のものだ。こうした「わかりやすさ」=通俗性は、いうまでもなくサブカルチャーの主要な特徴の一つである。別の角度から言い換えるならば、ここでは、「作品」というもののステータス自体が変容を被っている。すなわち、サブカルチャーにおける「作品」とは、個別的なものとして同定されるべきものというよりは、むしろ、数多ある「似たものたち」の群れの中に帰属すべきもの、そうした群れへと帰すことにより固有の輪郭を失い、匿名の厚みの中へと溶けていくべきものであるのだ4。
こうした匿名的な構造を考慮に入れるならば、必然的に、サブカルチャーの引用は、本質的にはそれと識別することが不可能なものであり、またそうすることが不要なものとなる。上述した三つの他にも、『常夏』には実際のところさらに多くの非明示的な引用が含まれているのではないかと推測される。それらを識別する作業は確かに、「元ネタ探し」として固有の快楽を備えたものであるだろうが、それに加われないことは、作品自体の受容に支障をきたすものでもない。
『常夏』における引用の機能を理解するために必要なのは、『時かけ』や『H2』といった個々の作品に関する知識よりも、むしろ上述のようなサブカルチャーの匿名的構造に関する認識だ。そして、サブカルチャーというものが今日の社会的現実の構成において果たしている役割の大きさを考えるならば、こうした認識は、批評的に必要なものといってよい。そう考えるならば、「引用の元ネタが分からないから分からない。世代的同質性を過度に前提としたネタの利用は共感の共同体に依拠するものであり、閉鎖的である」云々といった批判は、三浦がなしている作業に較べて、端的に知的に怠惰である。
付け加えていえば、サブカルチャーの匿名的な構造の利用が、単なる対象の性質への自動的な依存ではなく、それをなす三浦にとって本質的なものであることは、次の引用をみれば明らかであるだろう。
僕にとって、夏の思い出は、やっぱりフィクションの中にあって
とはいえ、もちろん僕にも、僕が実際体験した夏の思い出が存在します。
そして、誰かには誰かの夏の思い出がきっとあって
そしてそして、誰かの夏の思い出は、別の誰かの夏の思い出ではないわけで
だから、これは、僕と誰かと誰かと誰かと誰かと誰かと誰かとあなたの夏の思い出の物語です。
はじめまして、ロロです。
僕の夏の思い出が誰かの夏の思い出になったりならなかったり
あなたの夏の思い出がロロの夏の思い出になったりならなかったり、しますように、と
この舞台の上に、そういう、あいまいで、ぐっちゃぐちゃな、夏が、立ち上がりますように。
そんな、常夏です。
『常夏』の当日パンフレットに記されたこの一文は、匿名性ということが三浦のドラマトゥルギーの根幹をなすものであることを明確に語っている。まず、当初から、「夏」ではなく「夏の思い出」と述べられていることに注意せねばならない。すなわち、生(なま)の「事実」としての夏はもとより問題とされておらず、「思い出」、すなわち記憶のレベルに関わるものであり、したがって既にナラティヴ化されたものとしての夏こそが、三浦にとっての関心事であるということが、この時点で鮮やかに導入されている。その上で、そうした記憶の固有性が確認されつつ(「誰かの夏の思い出は、別の誰かの夏の思い出ではない」)、しかしそうした固有の記憶が連鎖的な反復の中で個別性を失う様が示され(「僕と誰かと誰かと誰かと誰かと誰かと誰かとあなたの夏の思い出」)、「あいまいで、ぐっちゃぐっちゃな、夏」=「常夏」のイメージへと収束、いや、むしろ溶解するのである5。現実と虚構、僕とあなたと(N人の)誰か、記憶と現在とが境を失い、「あいまいで、ぐっちゃぐっちゃ」に溶け合うこと。真夏の強烈な陽射しに照らされ、なんかもうわけがわからなくなること。夏の光のように非人称的な歓喜の中で、影も輪郭も蒸発してしまった無数の情動が意味なく疾走し、不注意に衝突し、うっかり結合し、これも運命と分離し、未練がましく再結合し、やがてぐっちゃぐっちゃになったりならなかったりすることの愉楽。『常夏』とは、こうした根本的に不穏で幸福な、匿名的なものたちの饗宴に与えられた一つの名である6。
さて、以上のように『常夏』の内的構造とそこにはらまれた一定の知的な戦略性を明らかにした上で、あらためて、より批判的な問題提起をなしておきたい。
一点目は、ロロの作品を一見したときに感じる「幼さ」という印象についてである。本稿ではここまで、そうした一見しての印象とは異なり、実際にはどれだけの知的な企みがロロの作品には込められているかということを明らかにしようとしてきた。つまり、それは「見た目に反して」の知的戦略性を析出しようとする作業であった。しかしながら、こうした「見た目に反する」水準の読解を行うこと(それに耐えうる構造が現に作品の内に組織されていること)は、決して「見た目」の問題を消去することにはならない。深層の構造とは別に表層の現われは残り続けるのであり、それ自体は、やはり「幼い」という印象を与えざるを得ないものである(念のために付言しておけば、深層と表層の間に位階関係はない)。これは確かに、印象の問題である。したがって、この水準を云々することは、最終的には私的な好悪の表明としての趣味判断にしか行き着かないものではある。しかしもちろん、趣味判断は――ある種の批評家がそう看做したがるような――瑣末な問題ではない。そしてこうした趣味判断に対して、表層における幼さの印象が強い負荷をかけるものであることは留意されるべきであるだろう。
第二に、よりはっきりと問題含みな点として、劇構造のある種の保守性ということを指摘しておきたい。先に私は、ロロの劇構造が「近代的なドラマトゥルギーや人物造形、またそれに則った台詞と演技の文体、セノグラフィのあり方を相対化するもの」であると書いた。 しかしながら、言い換えるならばそれらはまだ一つのドラマトゥルギーや人物造形、セノグラフィであるという意味で、すなわち、まだ一つの「再現」的なドラマ形式であるという意味で、一種の保守性を帯びたものでもある。もちろん、保守的であるということも決して否定的な評価と必然的に結びつくものではない。先に私はまた、ロロの作品がチェルフィッチュ的なものとは別のナラティヴを可能にするものであるとも書いた。保守性というのはこうした意味も含んでいる。チェルフィッチュやその系譜上に位置づけられうる作家たちにおけるような突出した形式的な試行はロロの作品にはいまのところ表立っては見られないが、演劇の課題はそれに尽きるものではないであろう。昨今の現代演劇の風潮からするならば、こうしたある種の保守性を引き受けつつ劇の言語を更新しようとするロロの試みは、むしろきわめて頼もしいものとも思える。近代的人間の相応に緊張に満ちた陰影をスキップする、致命的に軽薄な喧騒と親密に猥雑な脚力を加速し、より太く、屈強な劇の言葉を開拓してくれることをロロに期待したい。
1 これを支える登場人物の、レオス・カラックスの映画『汚れた血』のドニ・ラヴァンばりの疾走についても銘記しておきたい。同作が中核をなすカラックスの「アレックス三部作」は、その第一作目のタイトルをそもそも『ボーイ・ミーツ・ガール』としており、またそれを世界の価値の発生の源にまで高めたシリーズであったといえるだろう。
2 なお、この場合にも、その理解は必ずしも十全なものである必要はないし、さらにいえば十全であろうとするもの、原テクストの意味に忠実であろうとするものですらなくてもよい。むしろ、原テクストの意味を積極的に捻じ曲げ、ずらし、再配置することを目的とするものであっても構わないのである。それでも、これらは意味の水準に関わるという意味では、原テクストに対する――誤解を含めた――理解を要求するものと捉えることができる。
3 付言しておけば、ここで三浦が示しているのは単なる現実に対する表象(=漫画)の優位といったことではない。上述の通り、転倒は二重なのである。三浦にとって現実と表象とは、どちらが優位というものでもなく、というよりもそもそも截然と区別されるものですらなく渾然一体となったものなのである。
4『常夏』の登場人物たちの多くも、こうした匿名的な構造を利用している。肩にミサイルを搭載したブロッケンハンマーのようなキャラクターは――たとえ事実としてはそうなのかもしれないにしても――特定の元ネタを参照しているというよりも、そうした類型のイメージをこそ参照しているというべきだろう。
5 また、註3で述べたような、現実と表象が渾然一体となるというモチーフもここにはある。「夏の思い出は、やっぱりフィクションの中に」あると同時に「実際体験した」ものとしてもある。
6 匿名性ということに三浦が意識的であることを示す例をもう一つ挙げておこう。上述した『H2』の引用の場面において、「あたし、古賀にそっくりだし」(古賀は『H2』のヒロイン名)と嘯いていた貴子江は、続けて、「タッチもやる? いいよ、あたし元々南にもそっくりだからさ」と、あだち充の別作品のヒロインとも「そっくり」であることを主張し、その再現を提案するのである。これは、あだち充の画風のバラエティの乏しさ――そのためにキャラクターの顔が全て似てしまい、古賀にそっくりであるということはそのまま南にもそっくりであることになってしまう――を利用したジョークであると同時に、引用されるネタの根本的な交換可能性=非固有性を示すものと読むことができる。さらにいうならば、そもそもロロという劇団名からして、ある種の匿名的な効果を狙ったものではないだろうか。字面として、音としての記号的な抽象性に加え、□□□(クチロロと読む。その中心メンバーの一人は「三浦康嗣」であり、つまり、ロロの三浦直之とは苗字までかぶっている!)とあまりにも紛らわしいという点に、ロロという名に込められた匿名性への意志を、やや妄想的かとは思うが私は感じる。
- ロロ
- 2011年12月07日