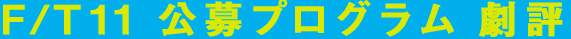子供を所有しないことはできるか (『おねしょ沼の終わらない温かさについて』)
<堀切克洋>
鳥公園は、劇作家・演出家の西尾佳織によって2007年7月に設立された「劇団」である。構成員は主宰の西尾と、俳優・デザイン担当の森すみれの二人だけなので、「劇団」というよりはユニットと呼ぶほうが適切かもしれない。俳優やスタッフの編成は、流動的である。西尾は、そのような「ゆるやかさ」を「公園」と呼ぶ。「三人以上の集団は苦手です。二人はぎりぎり好きです。〔......〕鳥公園は、一人でいて、それでいて人と一緒にいられるための場所です。出入り自由です」(鳥公園HPより)。
このような集団に対する問題意識は、F/T11「公募プログラム」枠内で上演された『おねしょ沼の終わらない温かさについて』(2011年10月19日〜24日、シアターグリーンBASETHEATER)という舞台作品でも主題的に描かれている。この作品には、「家族」という制度はすでになく、誰が母親で、誰が父親なのかもわからないような、数名から構成される小さなコミュニティがあるにすぎない。そして、その集落には「おねしょ沼」と呼ばれる沼があり、上方からは「ドロドロとしたもの」が垂れ落ちている。
妊娠はうんこである
舞台は、三人の女たち(井上知子、笹野鈴々音、島田桃依)が、東京という都市の生活における「漠然とした居心地の悪さ」を示唆しながら、だらだらと話している場面からはじまる。彼女たちは互いにT、L、Mと匿名的に呼び合っていて、話題はガールズトークらしく、セックスの話、妊娠・出産の話、子供の話がメインだ。しかし、雑誌「an・an」やテレビ番組「グータンヌーボ」で語られるような「女の幸せ」についての話ではない。
たとえばMは、「昨日」、恋人と別れたばかりである。しかし、泣きわめくわけでもなく、飄々としている。むしろ、ショックだったのは、本人によれば、セックスをしていたときに、恋人が実はいつも肛門に性器を入れていたことを知ってしまったからなのである。
M 〔......〕とにかくまあすごく、異物が挿入されている感。っていうのがひたすらあって。何というか、ああこれは物理だなーと思った。自分の体をあんなに「物」だって認識したのって初めてで、穴。に・なんか、ゴリゴリ。ダスンダスン振動。穴。ゴリゴリ。ダスンダスン。物理。
だけどね、気持ちよくも痛くもないんだけど、ふむわぁ〜とお尻のまわりがずっと、不安な感じ。ごめんなさいちょっと汚い話、便意を、もよおしてしま、う(呻き)〔......〕
このことは、付き合っていた男がアナルセックスを嗜好していたという日常的なエピソードではない(逆に、Mが快楽に至ることができなかったという話でもない)。Mは、肛門の周辺に「不安」を感じとっている。そしてその「不安」が、男性器と同様に「異物」である赤ちゃんを生み出すのである。
三人 ひ・ひ・ふー ひ・ひ・ふー M 私・は・考えます。集中・します・妊娠に。妊娠?出産?いや妊娠。そう妊娠。妊娠はうんこ。 L 名言が出ました。 三人 妊娠は、うんこ。 M そう、うんこなんです、子供ってものは。〔......〕だから私はいつまでも私で、子供はどこまでも異物で、私はどこまでいっても自覚のないお母さん!
三人がその場のノリで即興的なコントを演じるなかで、Mはこのような結論に達する。「私はいつまでも私で、子供はどこまでも異物で、私はどこまでいっても自覚のないお母さん」である、と。
子供は、親の自己実現や自己決定を妨げる「ネガティブ・ファクター」である。ただし、ひと昔前であれば、それは「仕事」と「子育て」という二項対立を前提としていた。つまり、子供は「仕事=自己実現」のためのネガティブ・ファクターだったはずである。女性にとって、「仕事を選ぶこと」は、それまで最初から失われていた道を開拓することであった。
文脈は少しずれるけれど、「胎児はじつはウンコである」の伊藤比呂美のエッセイもそういう時代に書かれたものだった。
しかし、ここで「私はいつまでも私」と自己規定してしまうMは、もはやそのような苦しみに苦しんではいない。何らかの仕事によって自己実現ができるとも考えていないし、かといって母親として子供に愛情を注ぐという道も選ぶ気がしていない。つまり、「女である」ということが招いてきた問題から、(生物学的には女であるにもかかわらず)距離を感じていることによって、「女になりきれない」のである。それゆえに、唯一の寄りかかる場所が、性別を取り除かれた「私」となってしまう。
社会はうんこである
このような中性的な(?)私にとって、あらゆる社会はそれ自体が異物感に満ちた塊として目に映る。なぜなら、自分の身体さえも「物」だと感じてしまう私にとって、私以外のものは当然のことながら「物」にすぎないからである。そのような「物」すべてを、「持っていても仕方がないもの」であると見なせば、物の所有に躍起になっている人々のことが遠く離れた存在に見えてくることだろう。
このような感覚は、現在の10代から30代にかけて広く共有されているのではないだろうか。マイホームは「過去の幻想」として葬り去られている。クルマが特別な乗り物であった時代もいまや昔の話だ。CDやDVDはレンタル、あるいはダウンロードで済ますことができる。不況の時代に相俟って、「不要なものは買わない」、「要らないものは捨てる」技術が称揚される。
デジタル化とエコロジー。
断捨離、あるいは三ない消費(「買わない」「持たない」「捨てない」)というのもあった。
人間関係もまた、ツイッターやフェイスブックによって可視化されている。一対一の濃密なコミュニケーションから、もう少しゆるやかな連帯へ、ということだろうか。
劇中の女たちは、このような価値観のもとで、親が子供を「所有」する――これは現実社会においては、ごく一般的なことであろう――ということに疑問を呈する。家庭教師のアルバイトで小学生を教えていた(ということは、そこそこの学歴である)Tは、生徒の母親が子供の成功(失敗)と同化していることに対して嫌悪感を感じる。
ああいうふうにはなりたくない、と。
いや、本当は、ああいうふうには「なれない」と感じているのだろうか? Lは、かつて不登校だった弟の「僕だって行けるもんなら行きたいよ」というダブルバインドの状態に対して、今更ながらの共感を告白する。動くことができない。何もしたくない。そうした倦怠感が、舞台の背景にあるのだ。この動けなさ、何もしたくなさを、どうすればいいのか?
おそらく、M、T、Lの三人――彼女たちはひとりの人間の多面的な現れというよりも、三人のやりとり自体が、現代日本の若い女性を象徴しているのだろう――は、取り立てて生活に困窮しているわけではない。また、バブル期に流行したような「私探し」を求めて奔走しているわけでもない。さらに、退屈な日常(=「終わらない日常」)に対して「非日常」を欲望しているわけでもない。
ここで、「うんこ」とは何かについて、少し冷静に考えてみたいと思う。
うんことは、限りなく稀なケースを除いて、人間の肛門から出される排出物である。しかし、別の角度から見てみると、うんこの特徴はその「所有できなさ」にある。もちろん、大きなうんこが出たときに、誰かに見せたいという欲望が猛烈に沸き上がってくることは、あるだろう。でも、そのうんこでさえも、流されて亡きものとなってしまうのである。わたしたちは仕方なくレバーを引く。まるで夜汽車で恋人を見送るように。
沼、あるいは所有しないということ
とにかく、三人は東京を出る決心をして、イシマツくんと呼ばれる髭をたくわえた大柄な友人(石松太一)のもとを訪れる。彼が「夜汽車で見送るべき恋人」かどうかはわからない(仲のいい友人であることは確かなようである)が、東京を離れる決心に至ったプロセスを(うまく整理できないながらも)「競歩」をしながら、必死に伝えようとする。
だって一回まちがったら戻れないって、怖くてしょうがないでしょ(T)。〔......〕だから私、あのお母さん責められないよ(M)。〔......〕だけどもう、私が、とか『私の』子供が、もっと少しでも安全で有利で条件のいい方へ、みたいなの、やなの〔......〕私は、もっと生きたい。もっと、いのち燃やして生きたい(L)。
彼女たちは、現状の社会システムの不備を厳しく批判することによって、大革命を起こそうとなど、思っていない。なぜなら、彼女たちもまたその社会の一員だからである。でも、何かを変えなければいけない、とは思っている。狭い劇場を延々と競歩によってぐるぐる回っているなかで、「わたしのもの」を増やすのではない仕方で生きるためには、どうしたらよいのか、考えている。
彼女たち、は、なぜ沼に、行ったのか。都市の、何かに耐えられなくなったから。〔......〕けどそれで、逃げ出す、っていうのは幼い。〔......〕だけどその中で、じゃあ一人だけで新しいものを始められるほどの才能は、ない、っていうか、才能の問題ではない。そういうシステムとか、社会とかっていうものはじわじわ時間かけて少しずつ少しずつ変わっていくものなので。そう、だけど女の人が、でも少なくともこれじゃだめだ、って。私もう信じられなくなってしまった。て言って、それをやめてみる。って、ことが、沼。逃げてる、って言われるでしょうか。逃げてるよって、言われるでしょうか。
これより先の冒頭の場面で、三人の女たちは「落ちている子供」に乗ったり、叩いたりする。この状況を解説をするように、ナレーター(伊藤俊輔)は上のように語っている。ここまで述べてきたとおり、三人は所有することに対する違和感を抱いてきた。そして、「所有できなさ」――すなわち「うんこの美学」なるもの――を貫徹しようと「沼」へと向かうのである。
麦ちゃんと初ちゃん
「沼」には、ふたりの姉妹が生活している。姉妹である麦(森すみれ)と初(寺田ゆい)は、まだ5才か6才といったところだろう。強気な初は、沼の水(?)を飲み干そうと、毎日ストローで「沼」を啜っている。麦はその姿を見て、いつもなんだか嫌な気分になっている。三人の女たちが、彼女たちの母親で、イシマツは「イシマツ」と呼ばれている(「沼」についてきてしまったらしい。エプロンをつけて女っぽい身なりになっているが、おそらく「父親」である)。
この共同体には、ときどきマルコスと呼ばれる陽気な若い男(吉田圭佑)が遊びにやってくるが、基本的には外部からの訪問者はない。M、L、T、イシマツ、麦と初の6人が家族のように暮らしている。この「沼」では死にかけている幼児の死体が洗われたり、女の子であるはずの麦の下腹部から「おちんちん」(かんぴょうで出来ていて、食べることができる)が生えてきたりと、多分に不条理な世界である。
さて、この作品後半である「沼」の場面は、いくつもの場面(対話)が断片的に展開していくのだが、ここでおさえておきたいのは、麦は初のことが大好きでたまらないのに、初は麦のその気持ちを受けとめることができない、という(恋愛相談でよくある)状況である。以下は、初とマルコスの会話。
マルコス ...えーと、麦ちゃんはあなたのことが好きで、でもあなたはその思いには応えられないと。だから僕をあてがいたい、って、そういうこと?〔......〕そっから逃れたい、というのがういちゃんの(望んでること)
〔......〕
初 麦といてもあたしは麦の望むようには応えられないから、申し訳ないなーと、いうか、なんか、あたしは参っちゃってる。
「沼」の人間ではないマルコスは、直後で「自分が、麦ちゃんにこうしてやりたいっていう積極的なものが、ないよね」とたしためる。逃げなんじゃないのかそれは、と。「沼」は、〈所有する-所有される〉という関係から抜け出してきた三人の女がたどりついた場所だったはずだ。しかし、その娘である初もまた同じ苦しみを覚え、「沼」の水を日々飲みつづけているのである。
一方、初が好きでたまらない麦のほうは、どのように描かれているか? 麦はイシマツを連れて散歩しにいった先で、「毎日毎日わたしの後ばっかついてきて、気持ち悪いんだよ」「嫌いだからどっかいっちゃいなよ」「毛が生えてるのが、嫌い」と、イシマツを置いて帰ろうとする。イシマツは悲しい気持ちで、無言になる。そして沈黙のあと、麦はこのように応答する。
麦 人にこういう風にするのってドキドキすんね。
イシマツ ああ...
麦 でももう少し、何か生じるかと思った。
〔......〕
麦 ういちゃんは、私にさっきみたいなこと、言わないの。
イシマツ 言って欲しいの?
麦 ううん。私は特に、何を言って欲しいとかなくて、ただういちゃんの思ってることが、もう少し外に出たらいいのになー、と思う。
「沼」は、T、M、Lの三人にとって、恋愛-結婚-出産を前提にした近代家族のあり方を支えている前提(「所有すること」)からの避難場所であった。しかし、この沼は、「人と関わることから逃げること」、もっと言えば、自分を「逃げる」ように仕向ける力なのである。
ふたつのユートピア
では、この力はどこからやってくるのか? それは、女性の身体である。「沼」は、うんこのようにというよりは、むしろオリモノのように――とはいえ、この感覚を男であるわたしが実感することはできないけれど――、おそらく、オリモノのように緩慢に、上から流れ落ちては、枯れることがない。それは、排泄という生理であると同時に、「所有できない」ものである。 もっとも、作品タイトルにあるように、「おねしょ沼」なのだからして、そのような解釈は誤っていると言うこともできなくはない。しかし、実は作品中に「おねしょ沼」という名称は一度も出てきていないことに加えて、上から落ちてくるスライム状の物体は、何がどうしたって、おねしょではない排泄物を想像させることだろう。その判断は、読者に任せたい。 ここで確認しておきたいのは、最後の場面において、2パターンの結末が提示されていることである。ひとつはT、M、Lの三人と「沼」の関係だが、彼女たちはすっかり老いてしまって――単純に時間が経過したのか、そうでないのかはわからないが、おそらく彼女たちは「枯れて」しまったのである――、みずからの半生を振り返る。
T 私、家族って信じてなかったのね。家族って、子供を育て上げるための制度でしょう。
M だから結婚もよく分かんなくて。だって結婚って、家族になるためにするわけでしょう?一緒にいたいだけだったら、ただ本人同士が一緒にいればいいもんねぇ。
L だけど恋愛は、いつか必ず終わるでしょう。そして私たちは別れるでしょう。だから私は、参ったなあー、と、思った。〔......〕
M だから今思うと、恋愛はいつも私の敵であったのだな。
T でも私たちはなんか、別れるとかないよね。
こうして三人は、ついに「沼」に肩まで浸かってしまう。男性であるイシマツと、ナレーター役のI(伊藤)は、取り残されてしまう。 彼女たちは、近代的な恋愛イデオロギー(ロマンティック・ラヴ幻想)を打ち破ることができたのだろうか? 恋愛の話になどならないガールズトークの場を、彼女たちはつくりあげることができた。にもかかわらず、彼女たちは「老いて」いる。何も所有しない。私は私のまま。彼女たちはいま、オリモノの沼で肩まで、オリモノのでなくなった身体を休めている。
この作品には、もうひとつの結末が用意されている。麦と初の「沼」との関係である。いま、沼にはこれでもかというほどの量のスライムが落ちている。初は相変わらず、「沼」の水を飲み干そうとしている。
麦 そしたら、初ちゃんの中にもういっこ沼ができるってこと?
初 そうそう。こいつがちっちゃくなればなるほど、あたしん中の沼は大きくなるわけ。
〔......〕
麦 じゃあ私は、初ちゃんの沼で、釣りするね。
初 はあ?
麦 で、とれた魚をその場で焼くね。
初 なんだよそれ(笑)
二人の他愛ない会話のなかで、「沼」は初の身体のなかに収められ、そこで麦は釣りをして、魚を釣って、挙げ句の果てには、定食屋さんを開くという。「所有すること」からの避難場所であった「沼」が、ここでは麦のユーモラスな空想によって一転、幸せな生活風景となる。ふたりはいつになく高いテンションで、寸劇を繰り広げるのである。
こうして見てみると、本作『おねしょ沼の終わらない温かさについて』は、最終的に男が世界から消え去るシスターフッドの劇であるようにも思われる一方で、現代の都市生活における「居心地の悪さ」を、排泄物をイメージ化した演出によって描いた作品であるのかもしれない。ともあれ、着想の原点には伊藤比呂美の一連の妊娠・出産・子育てエッセイや詩があったのだと思う。
ところで、わたしは伊藤比呂美のエッセイを読んだことがなかった。現在、中公文庫から『良いおっぱい 悪いおっぱい』(〔1985年〕、2010年)、『おなか ほっぺ おしり』(〔1987年〕、2011年)が再文庫化されているので手にとってみたのだが、伊藤が第一子を出産したのが1984年のこと。西尾が生まれた1985年とほぼ同時期である。
伊藤は中公文庫版で「25年後からの言及」として加筆を行っているのだが、本作品におけるイトウM、L、Tというのは、現代版(?)伊藤比呂美――つまり、「伊藤比呂美を読む西尾佳織」――であり、その子供である麦と初のふたりは、25年後(2036年)に「25年後からの言及」として言及される子供の姿であろうか? 『良いおっぱい 悪いおっぱい』を読むと、そういう想像力が刺激される。
西尾とそう年の違わないわたし自身も、2036年頃には(生きていれば)53才となっている。そのときに、わたし自身はどうしているだろうか? リューマチや神経痛に効く茶褐色の温泉にゆったり浸かっているだろうか? それとも定食屋を開いて店自慢の沼魚定食を来店客にふるまっているだろうか?
*本稿の引用箇所はすべて頒布版の上演台本による。
- 鳥公園
- 2011年12月19日