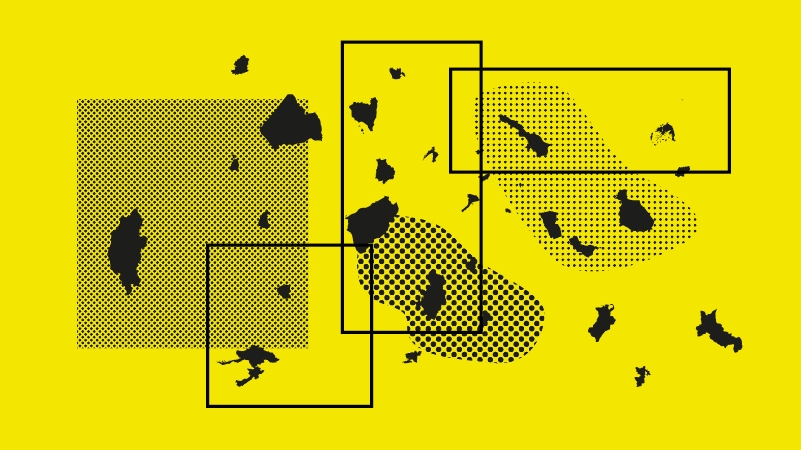『オールウェイズ・カミングホーム』、あるいは未来へと向けられた作品

日本・ポーランド国交樹立100周年記念事業の一環として、マグダ・シュペフト演出『オールウェイズ・カミングホーム』が、フェスティバル/トーキョー、ポーランドの国際文化交流を担うアダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート、ポーランドを代表する劇場のひとつであるTRワルシャワ劇場の三者の国際共同制作作品として、2019年11月8日から10日まで、東京芸術劇場シアターイーストで世界初演された(上演時間約90分)。原作者アーシュラ・K・ル=グウィンの知名度も手伝ったのであろう、客席は連日満席となった。2020年3月6日にはTRワルシャワ劇場でも公演が始まる。
本作品はSF作家ル=グウィンの同名の小説らしからぬ小説に基づいている。『ゲド戦記』(1968-2001)や『闇の左手』(1969)などの作品によって、日本でもよく知られる彼女は、1929年にカリフォルニア州バークレーに生まれ、2018年1月にオレゴン州ポートランドの自宅で亡くなったばかりである。『闇の左手』は、両性具有の宇宙人という設定を通じて、ジェンダーとセクシュアリティを問題化するものであったように、ル=グウィンは徹底したフェミニストでもあった。1985年に発表された『オールウェイズ・カミングホーム』は、今から2万年後のカリフォルニアをおそらくは舞台として、私たちの社会を特徴づけている科学技術のほとんどを失った後、自然との密接な関係のうちに生きる人類の末裔たちのポストヒューマン的社会を、民族学的調査研究の資料のかたちを借りて、描くものである(星川淳による翻訳が1997年に平凡社から上下2巻本として出版されているが、現在は品切れになっている)。
演出を手がけたのは、1990年にイェレニャ・グラに生まれ、ヴロツワフ大学ジャーナリズム学科でジャーナリズムとソーシャル・コミュニケーション、クラクフ演劇大学で演出を学んだ後、若手ながらもポーランド現代演劇を代表する演出家となったマグダ・シュペフトである。岩城京子による彼女のインタビューが明らかにしているように、ポストドラマ的な作品を多く手がけてきたシュペフトの美学と方法論の背景には、環境問題、ポストヒューマニズム、フェミニズムに彼女が寄せる関心がある。そんな彼女が新作をつくるにあたって、ル=グウィンの『オールウェイズ・カミングホーム』を選んだのは、ある意味では必然だったのだといえるかもしれない。この作品にも、(脱)人間中心主義、(脱)男性中心主義、(脱)科学主義、(脱)ドラマ演劇・・・・・・といった、既存の―社会的、科学的、文化的、演劇的―支配的ナラティヴからの脱却の試みが強く読みとられるからだ。
それに合わせて結成されたクリエーション・チームについても、脱序列化された独特の集団性を指摘できるだろう。演出家の周りには、振付のパヴェウ・サコヴィッチ、作曲のキシトッフ・カリスキ、舞台美術・照明・衣装デザインのミハウ・コロホヴィツ、映像の冨田了平という複数のクリエーターが集い、日本側から荒木亜矢子、稲継美保、鈴木奈菜の3名、ポーランド側からモニカ・フライチック、マテウッシュ・グルスキ、パヴェウ・スマガワの3名が出演した。そのなかでも特筆すべきはドラマトゥルギーの体制であろう。ポーランド側からウカッシュ・ヴォイティスコ(上演台本づくりも担当)、日本側から、東南アジアでの間文化的文脈での経験が豊富な滝口健、さらに2名のアシスタント・ドラマトゥルク(曽根千智、朴建雄)がつくという、きわめて手厚い体制が組まれた。日本・ポーランド両国において、そして両国の間で(しばしばskypeを介して)、そうした集団によるリサーチを重ねた上に出来上がった作品であるという。
この上演作品を特徴づけているのもまた、きわめて徹底した脱序列化、脱中心化である。直線的に展開するような物語は存在せず、言葉、身体、音楽、映像、セノグラフィが、そのいずれかが中心を占めることなく、詩的世界が紡ぎ出されていく。日本語・英語・ポーランド語の三言語が用いられるが、(東京公演での字幕は日本語と英語のみだが)その中のひとつがほかに対して優位な位置を占めることもない。パフォーマーの性差が強調されることもない。反面、そうした脱序列化、脱中心化は、言葉、身体、音楽、映像、セノグラフィは互いに深く結びつくことなく、そして観客を惹きつける求心的な強度を欠きつつ、単にバラバラに並置されているという印象を生み出しがちでもある。原作が日本語で上下巻2冊におよぶ長大な(そして後述するように、複雑な)叙事詩的テクストであり、必然的に一部の場面のみを抜粋して作品に採り入れることになるため、作品を構成する諸場面や諸要素の間の連関は、そしてそれによって作品に込められた意図も、なおのこと見えにくくなる。
だが、『オールウェイズ・カミングホーム』が現代以上に未来の観客に向けられた作品なのではないかと考えると、現代の私たちには縁遠く、そして理解しがたく感じられるのも、実はそもそも作品のつくり手が意図していたことであったのかもしれないと気づき、非常に納得がゆくようになると同時に、眩惑にも近い驚愕を覚えもするのである。というのも、ル=グィンの原作小説自体、手にとって読むとすぐに分かることだが、そう簡単には読み解けない、飲み込んで消化して、我が物とすることができない厄介な代物だからである。未来の人類は生活も思考の様式も現代人のそれとは大きく異なり、現代人には簡単には理解しがたい「ポストヒューマン」的存在であるという点によっても、その彼らが用いるとされるケシュ語という、まだ存在していない未来の言語で書かれたテクストを英語に翻訳したとされる言語学的特徴によっても(それがさらに日本語に訳されると、新たな屈折の導入によって見えにくくなってしまうが)、詩、戯曲、歌の歌詞、地図、用語解説(ケシュ語のミニ辞書)などの断片が並置された多元的なテクスト構成、少なくとも2人の語り手によって語られ、中心となる人物や物語を欠き、安直な感情移入を許さない物語構造によっても、原作において強調されているのは、現代にいる私たち読者が立っている場所からの距離だからである。
そもそもの原作が、小説の形式から逸脱しつつ、そのことによって小説の条件を問い直す小説であり、オリジナルにしてすでに翻訳されたテクスト、複数の屈折をうちに孕んだ作品であり、未来の人間と現代の人間の間のコミュニケーションの(不)可能性を読者に突きつけているのだ。そんなテクストを出発点として、マグダ・シュペフトが、演劇の形式から逸脱しながらそれによって演劇の条件を問い直す演劇、不可避的に翻訳と通訳に頼らざるを得ず、複数の中心と屈折を抱え込んだプロジェクト、舞台と客席の間のコミュニケーションの(不)可能性を問題化する作品を構想したのだと考えるならば、この作品が実は、おそるべき高度な水準で構想され、構築され、見事なまでに首尾一貫したドラマトゥルギーを備えたものであることが理解されるだろう。その一貫したドラマトゥルギー構造が、原作を必ずしも読んでいない観客、シュペフトのほかの作品を見ていない観客にも、その場で——上演の時間と空間、「今、ここ」において——理解されるものであったら、さらに大きな興奮が観客に与えられていたにちがいない。だが、その意味においても、『オールウェイズ・カミングホーム』は未来へと向けられていたのだ、といえるだろう。
参考ウェブサイト
フェスティバル/トーキョー・ウェブサイト
https://www.festival-tokyo.jp/19/program/always-coming-home.html
岩城京子によるマグダ・シュペフト・インタヴュー
https://www.festival-tokyo.jp/media/ft19/magda
CULTURE.PLウェブサイト
https://culture.pl/jp/artist/magda-szpecht
TRワルシャワ・ウェブサイト
http://trwarszawa.pl/en/spektakle/always-coming-home/
※記録写真は、ポーランド及び日本での稽古写真です。都合により公演記録写真の公開は控えさせていただきます。
藤井慎太郎 (Shintaro Fujii)
早稲田大学文学学術院教授(演劇学、文化政策学)。フランス、ベルギー、カナダなどのフランス語圏諸国・地域、および日本を中心として舞台芸術の美学と制度を研究している。共編著書に『The Dumb Type Reader』(Museum Tusculanum Press・2017)、『演劇学のキーワーズ』(ぺりかん社・05)、監修書に『ポストドラマ時代の創造力 新しい演劇のための12のレッスン』(白水社・13)、共同責任編集に『Alternatives théâtrales』numéro hors-série, “Scène contemporaine japonaise”(18 )、『Théâtre/Public』no.198, “Scènes françaises, scènes japonaises / allers-retours”(09)、共訳書にクリスティアン・ビエ、クリストフ・トリオー著『演劇学の教科書』(国書刊行会・09)、翻訳戯曲にワジディ・ムワワド作『炎 アンサンディ』『岸 リトラル』、ミシェル・ヴィナヴェール作『職さがし』など。
『オールウェイズ・カミングホーム』
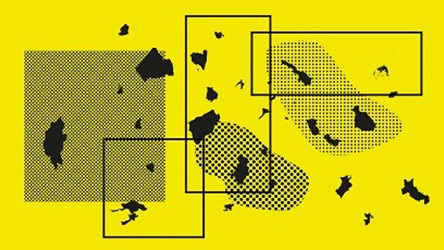
| 原案 | アーシュラ・K・ル=グウィン |
|---|---|
| 演出 | マグダ・シュペフト |
| テキスト&ドラマトゥルク | ウカッシュ・ヴォイティスコ |
| ドラマトゥルク | 滝口 健 |
| 日程 | 11/8 (Fri) - 11/10 (Sun) |
| 会場 | 東京芸術劇場 シアターイースト |
| 詳細はこちら |