「対立多発時代」に非人間的視点から世界に臨む演劇 ―マグダ・シュペフト インタビュー

フェスティバル/トーキョー19で新作を上演予定のポーランドの演出家マグダ・シュペフト。演劇とインスタレーション、ドキュメンタリーとフィクションなど、横断的な創作をする彼女に、これまでの活動やプロジェクトの構想について、TPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2019)会場で話を聞いた。
――あなたはヴロツワフ大学でジャーナリズムと批評を学んだのち、クラクフ国立演劇大学に入学しなおし、そこで演出家としての勉強と活動をはじめました。24歳のときにベルリンHAU劇場で発表された処女作『dolphin_who_loved_me』(2014)は、イルカの人間に対する恋愛感情を描くSF的物語であり、それでいてジャーナリスティックな批評性にも支えられた作品でした。SF的想像力とジャーナリスティックな批評性は、その後もあなたの作品では採用されつづけます。「サイエンス・フィクション」と「ノンフィクション」の双方の領域にまたがる作品を、あなたは好むのでしょうか。

シュペフト そうおもいます。そもそも『dolphin_who_loved_me』もSF的な内容でありながら、実話にもとづく芝居なんです。1950年代のアメリカでは、人間以外のものと会話をするための様々な実験が行われていたんですね。そのひとつがジョン・リリー博士という脳神経学者によるイルカとの対話実験だった。NASAの支援によって進められたこの実験で、リリー博士は通常は超音波で同族と会話をしているイルカに、頭のうえについている噴気孔を使って人間の言葉のようなものを発話できるように訓練した。それで実際にピーターという名のイルカと、トレーナーの女性のあいだには、なんらかの絆が築かれたわけです。けれどそれを「愛」と呼ぶのは、すこし人間中心主義すぎる考えだとおもいます。西洋演劇では伝統的に、つねに「人間にまつわる問い」が投げかけられてきました。ですから、人間以外のものを思考する演劇というのは極めて少ないのです。でも私の考えでは、人間以外の主体から世界を眺めることで、新しい知識が見えてくるはず。そのような思考を推し進めるのは、なにも科学者だけじゃなくてもいい。芸術や演劇も、非人間的主体について思考を深めてくべきだとおもっています。

――つまりあなたは非人間中心主義な、ポストヒューマンな視点に、アーティストとして興味を持ちつづけてきたということですね。
シュペフト そうです。もし私たちがイルカやネズミや樹木に寄りそった共感的思考を発展させたなら、いまよりもずっと世界に対する視点は豊かなものになるはずです。「自分だけの視点」に固執するなんて、アーティストとして退屈でしかたありません。ちなみに「人間以外のものからの視点」というテーマは、今回フェスティバル/トーキョーで発表する新作でも採用する予定です。
――今回、日本滞在中のリサーチでさまざまな背景をもつ女性にインタビューをされたそうですね。どのような質問を彼女たちに投げかけたのでしょうか。
シュペフト 「もし人間でなかったら、何に生まれたいですか?」という質問からはじめました。でもそうすると、ほとんどの回答者は「猫」って答えるんですね、もちろん(笑)。それで「猫以外だったら、何がいいですか?」と聞くと、いろいろとそこから考えが広がっていっておもしろかった。まずほとんどの回答者は、自然と関係のあるものを選びました。風、雲、川、霧。でもこの取材で大事なのは、どのような答えに辿りつくかではなく、その辿りついた自然物や動物の視点で世界を思考してみること。そのような非人間主義的な想像力を、対話者と広げていけたのが私にとってはすごくためになるリサーチでしたね。

――三宅島にも、リサーチに向かわれたそうですね。
シュペフト 日本で、まだ文明によって荒らされていない手つかずの土地を探していたんです。また、どこか「未来的」あるいは「異星的」な雰囲気のある場所も探していた。なぜなら今回の作品ではビデオ映像も使うんですけど、その映像によって、ここではないどこか別の世界という感覚を観客に与えたいとおもっているんです。それで三宅島のあまりふだんは目にしないような、大自然を映像におさめてきたんです。

――少し視点を変えた質問なのですが、ポーランド演劇では未だに古典的文献を舞台化することが多いですよね。しかし、あなたが選ぶ小説は、ミシェル・ウェルベック、デルモア・シュワルツ、今回のアーシュラ・K・ル=グウィンと「西洋演劇の正典」からは外れる異端の現代作家たちばかりです。なぜこのような作家たちを選択されるのでしょうか?
シュペフト ポーランド演劇界は、未だに18世紀浪漫文学を神聖視する傾向があります。アダム・ミツキェヴィチ、ユリウシュ・スウォバツキ、ジグムント・クラシンスキといったロマン派詩人の時代に、多くの演劇人はまだ生きている。だから私に言わせるなら、ポーランド演劇界の大きな問題は、「古典文学」に固執していること以上に、「過去」に幽閉されていることです。たしかにポーランドの過去は、悲しい歴史に染められており、未解決の問題も山積みです。けれど私たち演劇人は「未来」についても語っていいはず。トラウマ的なポーランドの過去を思考するのも大事です。だけど私と同世代の人間の多くは、自分がポーランド人であるというよりヨーロッパ人であると感じている。しかもインターネットが生まれたときから家にある環境で育ったことも、輪を掛けてわたしたちの世代を国際人にしています。ですからわたしはいつも、ポーランドに限定された問題ではなく、より普遍的なテーマの演劇をつくりたいとおもっているのです。
――日本ではポーランド演劇といえば、グロトフスキ、カントール、あるいはルパやワルリコフスキといった名前ばかりがあがります。しかし彼らは全員男性であり、あなたの父親世代よりも年上です。あなたは彼らから深い影響を受けているとおもいますか。
シュペフト もちろん、わたしは先行世代の演出家たちを尊敬していますし、多くを学ばせてもらいました。しかし直接的な影響となると、わたしはどちらかと言えば、欧州の振付家からインスパイアされることの方が多いとおもいます。たとえばグザヴィエ・ル・ロワ、ジェローム・ベル、メグ・スチュアートの作品は大好きです。彼らの作品は、古典的な意味でのナラティブがありません。より抽象的であり、だからこそ言葉を介さずに観客になにかを届ける力をもっている。そして私自身も、そうした古典的ドラマトゥルギーとは異なる方法論を採用するパフォーマンスを好むのです。

『The possibility of an island』Photo:Marta Ankiersztejn
――今回、あなたが日本で開催されたオーディションの文面にも「俳優とダンサー募集」と記されていましたね。つまりあなたは、テキストを頭脳的に解読するだけではなく、身体で何かを伝えられる人材を新作のために求めているわけですね。
シュペフト そうですね。特に原作小説があるときには、その小説からどれだけ遠くまでいけるか、ということを創作において大切にしているので、なるべく「他の言語」を話せる人に興味をもちます。ここで私が言う「他言語」とは、英語や日本語やポーランド語といった言語のことではなく、身体、表情、空間、照明といったものを使って生成する「演劇言語」のことです。ですから、小説のテキストを手にしたとき、それをダンスにしたり、モノローグにしたり、そこからインプロを生みだせたりする人材を私は好むといえます。あとは私の作品では、つねに俳優全員が舞台上にいることが多いので、自分の役柄について思考できるだけでなく、作品全体のコンポジションでなにが欠損しているか、全体を眺めて理解できる批評的思考性を持っていることが大事。自分の役柄に対する意識ではなく、作品全体の意識を解読できることが大事なんです。なお今回は日本人3人、ポーランド人3人という編成でプロダクションを手掛ける予定です。
――今回の新作制作は、アメリカのSF作家アーシュラ・K・ル=

シュペフト 第一には、やはり環境問題です。これは本作だけでなく、私の過去作品のほとんどすべてで採りあげている問題です。私にとって植物や動物は、つねにインスピレーションの源です。人間はあまりにも短期間で、この惑星を滅ぼしにかかっています。これはいま演劇で採りあげるべき、普遍的な問題だとおもっています。第二に、フェミニズムの問題です。あるいは反父権主義的視点と言い換えてもいいかもしれません。ほとんどのSF小説作家は男性です。しかしル=グインは数少ない女性SF作家として、フェミニズムの問題をかなり全面に押し出した作品を書いています。ただこれは私個人の視座であり、特にこうしたテーマ性に共感しなくても楽しめる作品にしようとおもっています。
――フェミニストでなくても、環境主義者でなくても、楽しめる作品だと。
シュペフト そうです。なぜならそれは、私個人の見解であり、観客に個人的見解を押し付けようとはおもわないからです。ご存知のように西洋古典演劇では、つねに物語のコアを成すのは「対立」です。ですからわたしは演劇学部での学生時代、先生に「あなたの作品には対立点が欠けている」と指摘されつづけてきました。でもそう言われるたびに私は「なぜ対立がないとダメなんだろう?」と逆に疑問におもってきました。これだけ世の中に対立が溢れている時代なのだから、演劇ぐらいは反対に、分断をうみださない内容にすべきじゃないのか。だからわたしの作品では、どんな政治的見解を持っている人間でも、上演時間の数時間、誰もが排除されずにコミュニティの一員になれるよう心掛けています。愛や、自然や、未来、といった誰もが共感できる普遍的内容を核心に据えるようにしているのです。
――近年のポーランドの右傾化にともなう政治的分断は、とくに目に余るものがあります。そうなると普段は分断されている人々を、同じ劇場空間に共存されるというだけで、極めて政治的な行為のようにもおもえます。
シュペフト そのとおりです。特に過去三年間、ポーランドは劇的な右傾化の道を進んでいます。そのため誰もが政治的見解を「述べねばならない」と信じており、大小様々な対立がそこら中で勃発しています。ですからポーランドで誰か初対面の人間に会ったとき、最初に思うことは「この人は政治的に右か左か」ということなんです。それがわからないことには、会話ができない。でも、これはハッキリ言って異常です。共産主義時代にも、たしかにポーランドは現状維持派とリベラル派のあいだで分断されていました。でもまだポーランドは貧乏な国だったため、生活レベルでお互いを支えあうコミュニティがありました。でもネオリベラル資本主義が完全に浸透したいまとなっては、誰も他人のことなど気にせずに生きています。政治的右傾化と資本主義のあわせ技で、私たちポーランド人は前代未聞の「対立多発時代」をいま生きている。だからこそ私は、演劇が今こそコミュニティを作るべきだとおもうんです。舞台上で対立を再生産するのではなく、共感や共鳴や共存を作る。それが現代社会において、演劇が果たす役目なのではないでしょうか。

●当プロジェクトは日本・ポーランド国交樹立100周年記念事業プログラムの一環として、TRワルシャワ劇場とアダム・ミツキェヴィッチ文化財団、フェスティバル/トーキョーとの国際共同製作で行われます。
撮影協力:TPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2019)・Kosha33カフェ
マグダ・シュペフト(Magda Szpecht)

1990年、ポーランド、イェレニャ・グラ生まれ。ヴロツワフ大学でジャーナリズムと批評を学んだ後、クラクフ国立演劇大学に入学し演出家としての活動を開始。2014年に発表した「私を愛したイルカ」はベルリンHAU劇場での100°Berlin Festivalで審査員賞を受賞。また、2016年国際演劇祭「神曲」の若手作家コンクール「パラディーゾ」で、「シューベルト。12人の演奏家によるロマンチックな第一弦楽四重奏」を上演し優勝。 シュペフトは、映像や音楽、実験的な振付、ドキュメンタリー要素を取り入れた演劇から、ビジュアルインスタレーションなど、幅広い形式で学際的な作品をつくる。また、演劇分野以外のアーティストとの共同制作や、観客と俳優を接続する空間でのパフォーマンスなど、従来の演劇システムから離れた実験的な作品制作を行う。
岩城京子
演劇パフォーマンス学研究者。二〇〇一年から日欧現代演劇を専門とするジャーナリストとして活動したのち、二〇一一年よりアカデミズムに転向。ロンドン大学ゴールドスミスで博士号(演劇学)を修め、同校にて教鞭を執る。専門は日欧近現代演劇史。及び、哲学、社会学、パフォーマンス学、ポストコロニアル理論、などに広がる演劇応用理論。単著に『日本演劇現在形』(フィルムアート社)等。共著に『Fukushima and Arts – Negotiating Nuclear Disaster』(Routledge)、『A History of Japanese Theatre』(ケンブリッジ大学出版)など。二〇一七年に博士号取得後、アジアン・カルチュラル・カウンシルの助成を得て、ニューヨーク市立大学大学院シーガルセンター客員研究員に。二〇一八年四月より早稲田大学文学学術院所属 日本学術振興会特別研究員(PD)。
オールウェイズ・カミングホーム
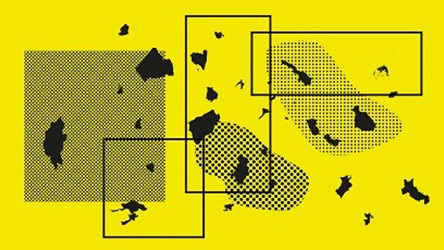
| 演出 | マグダ・シュペフト |
|---|---|
| 出演 | 荒木亜矢子、稲継美保、鈴木奈菜、モニカ・フライチック、マテウッシュ・グルスキ、パヴェウ・スマガワ |
| 日程 | 11/8 (Fri) 19:00 11/9 (Sat) 15:00★ 11/10 (Sun) 13:00 ★=終演後、ポスト・パフォーマンストークあり |
| 会場 | 東京芸術劇場 シアターイースト |
国際舞台芸術祭 フェスティバル/トーキョー19
| 名称 | フェスティバル/トーキョー19 Festival/Tokyo 2019 |
|---|---|
| 会期 | 令和元年(2019年)10月5日(土)~11月10日(日)37日間(予定) |
| 会場 | 東京芸術劇場、あうるすぽっと、シアターグリーンほか |
概要
フェスティバル/トーキョー(以下F/T)は、2009年の開始以来、東京・日本を代表する国際舞台芸術祭として、新しい価値を発信し、多様な人々の交流の場を生み出してきました。12回目となるF/T19では国内外のアーティストが結集し、F/Tでしか出会えない国際共同製作プログラムをはじめ、劇場やまちなかでの上演、若手アーティストと協働する事業、市民参加型の作品など、多彩なプロジェクトを展開していきます。
オープニング・プログラムでは新たな取り組みとして豊島区内の複数の商店街を起点とするパレードを実施予定の他、ポーランドの若手演出家マグダ・シュペフト(資料)による新作を上演いたします。
2014年から開始した「アジアシリーズ」は、「トランスフィールド from アジア」として現在進行形のアジアの舞台芸術やアートを一カ国に限定せず紹介します。2年間にわたるプロジェクトのドキュントメント『Changes(チェンジズ)』はシーズン2を上映予定です。
