作品と観客をつなぐ“契約”のために舞台美術ができること ――セノ派・佐々木文美インタビュー

舞台美術家コレクティブ「セノ派」による企画「移動祝祭商店街 まぼろし編」が、特設ウェブサイトを中心に展開されている。「顔ハメパネル」と「QRコード」を活用した作品を制作した佐々木文美は、観客の想像を促すことが舞台美術の使命だと語る。「快快」の一員として狭義の演劇に限らずさまざまな作品に携わってきた佐々木は、どんなところに舞台美術の力を見出しているのだろうか。
観客を置いてけぼりにしないこと
――佐々木さんは2004年の旗揚げ時から快快で活動されています。快快ではいわゆる「舞台美術」に限らず作品制作に携わることが多いと思いますが、いつ頃から舞台美術を意識されるようになったのでしょうか。
快快に入るまえは映像をつくろうと思っていたこともあって、最初から演劇に興味があったわけでもありませんでした。ドキュメンタリーをつくりたくて大学の映像演劇学科に入ったんですが、大学の卒業制作にあたってたくさんの人たちと共同制作したほうがいいなと思って。そのときに参加したのが小指値(2008年に快快に改名)の旗揚げ公演でした。面白いメンバーがたくさんいるなかで自分がどんな役職を担うか考えたときに、舞台美術かなと。でも、きちんと舞台美術を意識するようになったのは2013年ごろですね。それまで快快ではそれぞれが企画もオーガナイズもするし、みんなで制作することも多かったですし。2013年ごろに東京ワンダーサイトのレジデンスプログラムに参加した際に、「アーティスト」という肩書がしっくり来ず、自分のつくる展示を演劇やパフォーマンスのようなものとして捉えてもらううえで「舞台美術家」と名乗るのは面白いかもと思ったときから舞台美術を意識するようになりました。でも、もともと役者を乗せる舞台をつくるのは面白いと思っていて。役者の気分をノせるものでもあるから、ムードをつくる役割でもある。いろいろな作品をつくるうえで、どんなときでも舞台美術なんですと説明をつけていくのはよさそうだなと。
――それ以降はつくり方にも変化が生じましたか?
変わっていったと思います。舞台美術家と言うようになってからはとくにお客さんの存在を意識するようになりました。まずお客さんの目線を考えて、10度上向きとか下向きとか、どんな姿勢でお客さんが作品に参加するのか考える。それを言葉にすることに対してもポジティブになったと思います。観客の比重が大きくなりましたね。ただ、小指値(現・快快)に入るまえにパリで「ヌーヴォー・シルク」を観たとき、いろいろな動きを見るために首を動かす動作が入るだけでいわゆるふつうの舞台鑑賞とは異なる体験が生まれることに気付いたこともあり、お客さんの目線みたいなものはずっと意識していたかもしれません。
――近年は杉山(至)さんが率いる工房「六尺堂」にも参加されていますよね。ほかの舞台美術家の方との交流も増えていそうです。
六尺堂に参加したのは数年前ですが、もともと恐れていたんですよね。わたしは舞台美術の知識も技術もないですし、むしろプロの演劇人になったら普通のお客さんを置いてけぼりにしてしまいそうだなと思っていて。自分が「演劇」に染まるとお客さんのことが見えなくなってしまうかもと。でも、友達の手伝いでたまたま六尺堂を訪れた際に至さんが六尺堂のコンセプトを書いた張り紙を見たら、自分とはぜんぜん考え方が違うんだなと思えた。ぜんぜん違うならむしろ友達になりたいと思って参加することにしました。ただ、わたし自身はモノをつくるのが苦手で。人が「舞台美術」という言葉から思い浮かべるような仕事がぜんぜんできないので申し訳ないんですけど(笑)。

観客との共犯関係をどうつくるか
――ふつう「舞台美術」というと舞台上の美術セットをつくる仕事だと思われてそうですが、佐々木さんはべつのことをしているのでしょうか。
一般的な舞台美術のイメージとは違いますね。「お盆の上に飾りつけをしてほしい」というオーダーが舞台美術家への相談として多いと思うのですが、わたしはそのオーダーには応えられない。それって空間の怖さから逃げてるだけじゃないですか。うしろの把握できない空間が怖くて壁に背中をつけちゃう子どもがいるように、何もない空間ってすごく怖いものだと思うんです。でもそれこそが空間の本質でもあるから、単にその怖さを取り除くだけの作業はできないなと。
――「飾りつけ」ではないとすれば、佐々木さんはどう舞台美術へアプローチしているのでしょうか。
舞台美術の完成する場所はお客さんのイメージのなかだと思うので、想像を促すことは意識しています。演劇は目だけじゃなくて耳や皮膚など身体全体で感じているし、いままでの経験やその日の服装によっても感覚は変わりますよね。まずお客さんが劇場に入ってきて作品を観たいという気持ちを盛り上げることから始まって、最終的に身体のなかに何かが立ち上がっているような体験をつくりたいと思っています。
――舞台美術に取り組むうえで、何か影響を受けた作品や体験はありますか?
作品ではないんですが、印象に残っていることはあります。小学6年生のときに新しい家に引越したんですが、そのときに両親が「この家は子どもたちが絶対にグレない家です。さあ、なぜでしょうか?」と問いかけてきて(笑)。どうやら子どもが自分の部屋から玄関に行くまでに必ず食卓を通るようになっていて、母や父と目が合う導線が設計されていたらしいんです。顔を合わせざるをえないから、挨拶も無視しづらいし悪いことをしようという気持ちも半減する。親と会っちゃうアフォーダンスがあるというか。それは両親からかけられた魔法のようなものだったなと思います。空間を考えるうえで、身体や眼差しの重要性はそのころから何となく感じていたのかもしれません。
――観客の想像を促すことだったりアフォーダンスだったり、観客とのコミュニケーションを意識することが多いということでしょうか。
コミュニケーションって言葉はよく使いますし、すごく重要だと思います。演劇って、観るのに高度な技術が必要だと思っていて。まず作品と共犯関係を結ばないといけないじゃないですか。ゲームなら画面の中のプレイヤーに自分を投入すればいいけれど、演劇は同じ地平に立っている人に憑依しなきゃいけないし、作品の見方やルールのつじつまを合わせなきゃいけない。快快や、快快の元メンバーですが、篠田(千明)とよくお客さんとの共犯関係を結ぶ「ゼロ地点」をどこに設定するのかよく話していました。ゼロ地点は序盤でも終盤でもいいけれど、どこでどうお客さんと関係を結ぶのかが重要。歌舞伎や伝統芸能はそのルールが決まっているのに対して演劇やパフォーミングアーツは設定が自由なので、毎回新しい“契約”を結ばないといけないですよね。

「パーティ会場」としての作品
――「契約」というのは面白いですね。去年のF/T19で披露した「移動祝祭商店街」のように野外の移動型パフォーマンスだとまた感覚も変わりそうです。
ぜんぜん違いますよね。お客さんの集中力は確保できないので、昨年はとにかく見た目がキャッチーなものをつくることを意識していました。舞台美術の使命は人に想像させることですし、去年はまちの人から友達になりたいみたいな感覚をもってもらおう、と。パフォーマンスを行う側が率先して作品の世界に入り込んでしまうのではなくて、スタッフとしてお客さんに声をかけながらどんどん引きずり込んでいくようにしていましたね。
 F/T19 『移動祝祭商店街』(写真:合同会社アロポジデ)
F/T19 『移動祝祭商店街』(写真:合同会社アロポジデ)
――今年の「移動祝祭商店街 まぼろし編」ではさらに作品形態が変わりますよね。佐々木さんの「みんなの総意としての祝祭とは」では、まちなかの顔ハメパネルとそこに印刷されたQRコードからアクセスできる映像をつくっています。
まちにQRコードのついた顔ハメパネルを置いていて、顔をはめて写真を撮るとQRコードもスキャンされて映像が再生されるようになっています。パネルの置かれた場所で開催される祝祭の雰囲気を説明するような動画をつくっていて。旅番組のリポーターのような形で祝祭の様子をレポートすることで、お客さんに脳内祝祭を体験してもらいたいなと。ちなみに、動画の音声はすべてエスペラントになっていて、日本語の字幕をつけています。
――なぜエスペラントを選ばれたんですか?
今年の春ごろからエスペラントが気になっていたというのが大きいのですが、作品がオンライン化していくことを考えると、日本以外の人にも見せられるかもと思ったんです。とはいえ外国の方向けに英語を選択することにも疑問を持って、「平等」というワードを意識していたのでエスペラントを選びました。大塚には天祖神社があったりモスクがあったり、いろいろな宗教の人が集まっているんですが、制作を進めながら宗教について調べるなかで、翻訳という行為の面白さを実感しました。預言者は神様の言葉の翻訳者だし、預言者の言葉を多くの人に広めるときにも翻訳が生じますよね。
――たしかに大塚は海外の方も多いですよね。去年から引き続き同じ地域で作品をつくることで、コミュニケーションの可能性も広がっていそうです。
商店街の人たちと話すのはすごく楽しいですね。ただ、去年は実際に商店街を拠点に作品をつくっていたので自然とコミュニケーションが生まれていたのですが、今年はないのでもっとコミュニケーションの場をつくりたいなと思っています。映像を撮影するときもなるべく通りがかった人を作品に巻き込んでいきたくて。リサーチによってつくった内容をただ映像で表現するだけじゃなくて、たまたま映っちゃったものを積極的に取り入れるというか。顔ハメパネルはまちに置かれるものですし、展示している最中もまちの人がどんどん入ってこれるような余地を生み出せたらと思っています。決まったものを提示するのではなく、作品が「パーティ会場」になるような空間をつくっていきたいんです。

佐々木 文美

1983年鹿児島県生まれ。多摩美術大学 映像演劇学科卒業。快快メンバー。 FAIFAIでの演劇制作の他、個人的に演劇、ダンス、コンサート、展示など様々な企画に舞台美術担当として参加している。近年の参加作品として、F/T17まちなかパフォーマンスシリーズ 快快「GORILLA ~人間とは何か~」、2018年AAF戯曲賞受賞記念公演「シティIII」、2019年快快「ルイ・ルイ」 等。大好きなホームパーティーがなかなかできないので最近は快快の役者である山崎皓司、映像作家の玉田伸太郎と、ラジオ「ポテトタイム」を人知れず配信している。
もてスリム
1989年、東京生まれ。おとめ座。編集者。 トーチwebでシリーズエッセイ『ホームフル・ドリフティング』連載中。
舞台美術家集団が見出す “景”がまちと人にあらたな縁を結ぶ
『移動祝祭商店街 まぼろし編』

| 企画デザイン | セノ派 |
|---|---|
| 日程 | 10/16 (Fri) - 11/15 (Sun) |
| 会場 | 特設ウェブサイト、豊島区内商店街、F/T remote(オンライン配信) |
| 詳細はこちら |
商店街に散りばめられたまぼろしの祝祭をもとめて
『移動祝祭商店街 まぼろし編』みんなの総意としての祝祭とは
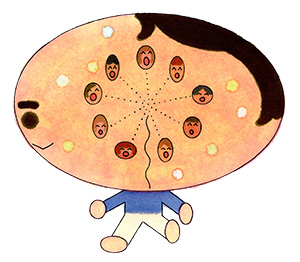
| 企画デザイン | セノ派 佐々木 文美 |
|---|---|
| 日程 | 10/16 (Fri) - 11/15 (Sun) |
| 会場 | 特設ウェブサイト |
| 詳細はこちら |
人と都市から始まる舞台芸術祭 フェスティバル/トーキョー20
| 名称 | フェスティバル/トーキョー20 Festival/Tokyo 2020 |
|---|---|
| 会期 | 令和2年(2020年)10月16日(Fri)~11月15日(Sun)31日間 |
| 会場 | 東京芸術劇場、あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)、トランパル大塚、豊島区内商店街、オンライン会場 ほか ※内容は変更になる可能性がございます。 |
概要
フェスティバル/トーキョー(F/T)は、同時代の舞台芸術の魅力を多角的に紹介し、新たな可能性を追究する芸術祭です。
2009年の開始以来、国内外の先鋭的なアーティストによる演劇、ダンス、音楽、美術、映像等のプログラムを東京・池袋エリアを拠点に実施し、337作品、2349公演を上演、72万人を超える観客・参加者が集いました。
「人と都市から始まる舞台芸術祭」として、都市型フェスティバルの可能性とモデルを更新するべく、新たな挑戦を続けています。
本年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、オンライン含め物理的距離の確保に配慮した形で開催いたします。