『演劇書簡 -文字による長い対話-』 応答:山﨑健太

『演劇書簡 -文字による長い対話-』 山﨑健太の応答
「見ようにも何も見えないのに当たり前のように何かを見ようとする」。 マレビトの会『福島を上演する』の上演に立ち会う観客の営為を端的に表す言葉だ。それが「当たり前に」なされるかどうかは演劇への、あるいはマレビトの会の手法への習熟の度合いによるだろうが、いずれにせよ演劇の観客は大なり小なり「そこにはないもの」を舞台上に見ている。いや、観客だけではない。舞台上の俳優もまた、「そこにはないもの」を見ているはずだ。
このように論じてみればそれは至極「当たり前」のことのようにも思えるのだが、松田の言葉がどこか奇妙に感じられるのは、実のところこの演劇書簡においては「見ること」がほとんど最初から最後まで俳優の問題として語られているからだ。冒頭に引いた言葉も、そもそもは「上演のなかにいる俳優はいったい何を見ているのだろうか」という問いへ答えるために、木下恵介の映画『野菊の如き君なりき』を経由して引き出されたものであった。「見ること」が問題とされる以上、そこには常に「見るもの」と「見られるもの」があり、ゆえに松田の文章のそこここに見るものとしての「観客」の存在は感じられる。しかし論じられているのが観客の問題で(も)あることは、書簡の実質的な結びの段落に至ってようやく明示されるのだ。「 無論、これは、俳優のことのみについて述べているのではない。何よりも、演劇を見るものたちのほうに生じている未知なる経験なのである」という松田の言葉は、書簡全体の読み直しを読者に促す。
つまり、松田の演劇書簡は一度目は俳優論として、二度目は俳優論を経由した観客論として読まれるよう書かれている。単に俳優の営為と観客のそれとが同一のものであると主張しているわけでないのは明らかだ。松田はなぜ、このような奇妙なやり方で演劇をめぐる経験について語るのだろうか。
ところで、この文章が「書簡」という形式によって規定されていることもまた、相当に奇妙な事態である。そのような体裁をとってはいないものの、この文章もまた一義的には松田の演劇書簡への応答であり、松田に宛てられた「書簡」なのだ(もちろん、同時に多くの人に読まれることを前提としたものでもある)。松田の演劇書簡についても同様だが、宛先は私一人ではない。六人の異なる人間に同一の文面が宛てられているというこの事実は、私に何か演劇的な手触りを感じさせる。それはまさに宛先の問題なのだと思う。松田の言葉は私に向けられたものでありながら私に向けられたものではない。
書簡の言葉が読まれるとき、そこではある具体的な手触りを伴った二つの「声」が入り交じる。書き手の「声」を読み上げる読み手の「声」。あらゆる文章がそうであると言えなくもないが、個人間で交わされる書簡と比較すると、たとえば書籍は広く様々な読み手に開かれている。そこに初めから具体的な「声」の手触りを想定することは難しい。匿名的な、無数の「声」の集合体が漠然と想像されるばかりだ。
戯曲は読み手として特定の個人を想定しない。あて書きという形で特定の俳優に演じられることを前提に書かれる戯曲はあるが、それが戯曲として残るのであれば読み手を特定することは原理的に不可能だ。だが、上演ということを考えるとき、そこには常に具体的な「声」が想定され、存在している。不特定の、しかし具体的な「声」。それらはやがて戯曲の書き手の「声」と、登場人物たちの「声」と入り交じることになる。
「母を嫁がせる」という松田の願望は、戯曲の持つこのような性質と呼応しているように思える。「せる」という助動詞は、たとえば「やらせておきなさい」という形で使われることがあり、英語のletに当たるそれは「容認」の用法などと説明される。「容認」と言ってしまうと「使役」の用法と同じくそれをする側の優位が強調されてしまうが、そこにあるのは一種の断念でもあるだろう。自らの意思が及ばないことを受け入れること。
しかも、松田は自らの願望の成就を望まない。問われるのは「母を嫁がせる、という願望を有機的に成就させるというよりも、非有機的なものへ変貌させ形式や領域の確定できない欲望とするにはどうすればいいのか」だ。松田の「個人的で、家族的な願望」は、宇多田ヒカルの声を通して「得体のしれない欲望」として松田のもとに再帰したのだという。願望の成就は(それ自体が主体的な意思の達成を意味するがゆえに)先延ばしにされ続ける。
ならば、問題とされているのはある主体とあるものごととの一対一の関係ではない。『福島を上演する』は劇作家に、戯曲の執筆前に福島に取材することを必須の条件として課している。福島で何らかの出来事に立ち会った劇作家は戯曲を書き、戯曲を読んだ俳優はそれを上演し、上演に立ち会った観客は感想を誰かに話す(かもしれない)。ある二項の関係は常に第三項を巻き込む形に展開し得る。松田はすでにそのことに触れていた。
福島の出来事と作家との、戯曲と俳優との、上演と観客の感想との間に生じる断絶は、そうして「視界をひら」くための回路となる。 私が2017年の『福島を上演する』に寄せた「想像せよ、それでもなお」というテキストは、『福島を上演する』の取り組みに、不可能を知りながらそれでも想像し続ける、言わば非当事者の倫理を見るものだった。人は誰しも自分以外の人間の非当事者でしかない。同時にそれは、どこまでいっても自分自身の当事者であることから逃れられないということでもある。非当事者の倫理と表裏一体の当事者の倫理。「出来事の演劇」は、その閉じられた回路から踏み出そうとしているように思える。
p.s.
お返事遅くなりまして失礼しました。松田さんが書簡の中で宇多田ヒカルやハライチに触れていたように、私もいくつかの固有名詞を記してこの書簡を終えたいと思います。 ナシーム・スレイマンプール×ブッシュシアターの『NASSIM』はご覧になったでしょうか? ナシームの言葉を俳優が語り、その場に観客が立ち会うという、まさにそれだけのことに賭けられているこの作品は、現れこそ異なれど、「出来事の演劇」と問題意識の一部を共有しているように思われました。
あるいは落合陽一+清水高志+上妻世海『脱近代宣言』。この書簡を書くのと並行して第3章「現象to現象の世界へ」を読んでいたのですが、そこに登場する落合陽一氏の《ReverseCAVE》(2017)という作品(それは「ヴァーチャル・リアリティの像をVRゴーグルで見ていて、それをさらに第三者が外から眺められる作品」だと説明されます)は、松田さんの書簡が示唆する入れ子構造を可視化したもののように思えました。ここで展開される様々なトピックや概念はそのまま、ちょうど今日読みはじめた上妻世海『制作へ』へとつながっているようです。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』の検討にはじまる「制作へ」と題された冒頭のエッセイもまた、見ることの二重性をめぐる思考から展開していきます。 松田さんからの書簡や『福島を上演する』の上演が私に開いたこれらの回路がどこにつながっているのか。楽しみにしながら本の続きに戻ろうと思います。
カバー写真・F/T18『福島を上演する』 撮影・西野正将 文・山﨑健太
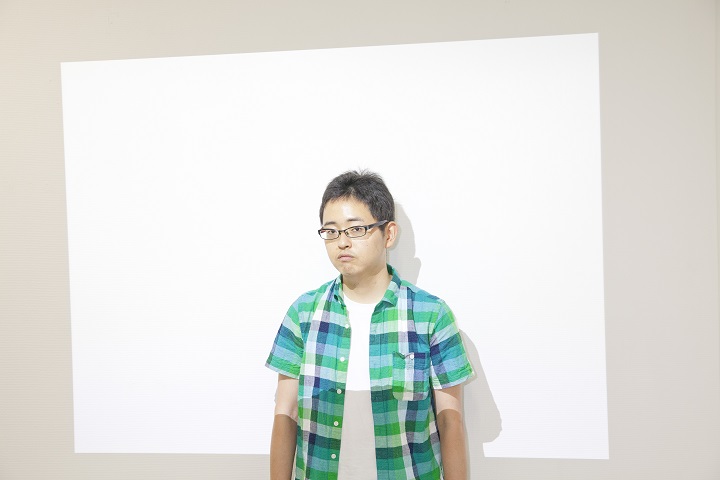 photo: Arata Mino
photo: Arata Mino
山﨑健太(やまざき・けんた)
1983年生まれ。演劇研究・批評。演劇批評誌『紙背』編集長。WEBマガジンartscapeで短評連載中。
『演劇書簡 -文字による長い対話-』
マレビトの会『福島を上演する』 作・演出:マレビトの会

| 公演名 | マレビトの会 『福島を上演する』 |
|---|---|
| 日程 | 2018.10/25(Thu)19:30・ 10/26(Fri)19:30・ 10/27(Sat)18:00★・ 10/28(Sun)14:00★ |
| 会場 | 東京芸術劇場 シアターイースト |
フェスティバル/トーキョー
フェスティバル/トーキョー(以下F/T)は、同時代の舞台作品の魅力を多角的に紹介し、舞台芸術の新たな可能性を追求する国際舞台芸術祭です。10周年、11回目の開催となるF/T18は、2018年10月13日(土)~11月18日(日)まで、国内外のアーティストが結集しました。
F/Tでしか出会えない国際共同製作プログラムをはじめ、野外で舞台芸術を鑑賞できる作品、若手アーティストと協働する事業、市民参加型イベントなど、多彩なプロジェクトを展開していきます。


