家としての言語:F/T18『NASSIM』の体験から
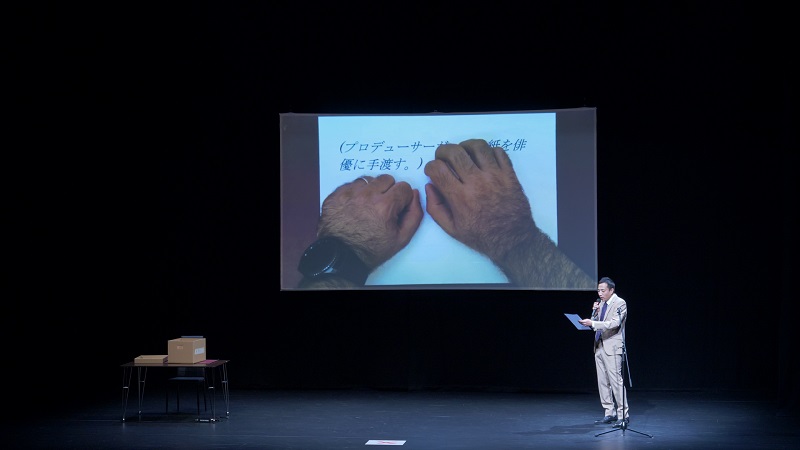
家としての言語:F/T18『NASSIM』の体験から
NASSIMの「家」に入る わたしは演劇の人間ではない。美術作品について論考を書くということは学生の頃からこれまで幾度となく行ってきたし、自分自身で制作した作品を展示してきた経験もあるが、演劇については正直なところ全くの素人である。
2018年の夏、そんなわたしのところに、イランの劇作家ナシーム・スレイマンプールの作品『NASSIM』に出演してくれないか、という依頼メールが飛び込んできた時には一瞬目を疑った。しかし、フェスティバル/トーキョー実行委員会の担当者、荒川真由子さんから送られてきた丁寧なメールを読み進めていくうちに、むくむくと興味が湧いてきた。
【引用はじめ】 言葉が通じないながらも投影される指示を通してナシームと打ち解け、だんだんと分かり合っていく感覚を観客とも共有できるような柔軟な方がとても必要な作品となっています。 (…)他者同士が分かり合うにはどうしたらいいのか、この漠然とした問いに対してドミニクさんとであれば一緒に思考することができると思い、お声掛けさせていただきました。 今回も国境を超えて、遠い国の青年、ナシームとともに本来人々を隔てるはずの言葉が、いつの間にか自分たちを結びつける、優しい時間をいっしょに形作っていただければと考えています。 【引用終わり】
言葉が世界を「分ける」ことと同時に、異なるもの同士を「結ぶ」作用があることについて、わたしは最近論考を重ねてきたので、戯曲の内容は分からないが、その志向性には強く関心を抱いた。しかし、それでもわたしは訓練を受けたパフォーマーではない、なぜわたしに依頼をしたのかと荒川さんに聞いたら、次のようなお返事を頂いた。
【引用開始】 ドミニクさんはポリグロットのご両親のもとで育ち、1つの言語だけではない環境の中で育ちながら自分の立ち位置をどのように確認してきたのか、また、自分の持っている「感じ」を様々な言語、または文化の違いの間でどのように変換してきたのか、演目と直接関係はないかもしれませんが、この演目を通して、ぜひナシームと対話していただけたらと思い、お声がけさせていただきました。 【引用終わり】
なるほど、ナシーム・スレイマンプールの経歴を調べてみると、個人的に共感を覚えるところがある。パスポートを取得するために必要な兵役を拒否したことで長年国外に出ることを禁じられ、外国語である英語で自作の戯曲を書いてきたという。わたしの場合は日本とフランスという二つの文化のあわいで育ち、日本語と仏語のどちらも母語であると同時に異国の言語でもあるというニュアンスのなかで生きてきたため、ナシームがおそらく経験してきたであろう「言語との距離」ということはよくわかる気がした。
フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズは、小説『白鯨』を書いたハーマン・メルヴィルの使った「outlandish」という表現に注目している。それは「この、私の属している世界の外にあるもの」という形容詞だ。「私が属している世界」という言葉を「領土」と言い換えれば、領土とは常にその内と外によって規定される。ドゥルーズは、ある主体がそれまでの慣習によって固定化された領土の外へと逸脱する力のことを「脱領土化」と呼び、領土化・脱領土化・再領土化という反復的なプロセスが主体の生成変化(devenir)を決定づけると考えた。
ドゥルーズにとって、「領土」とは、人間にとっても、他の生物にとっても、「家」と呼べる場所を指している。「家」の内と外の境界のうえに立つことによって、うちなる「家」と外部の世界の輪郭がはっきりと認識される。そうやって境界線を内へ外へと移動する時、動物や植物、菌類といった多様な生命体は、その身体に固有な表現をさまざまにおこなう。歌をうたう、色を発現する、姿勢が変わる。捕食したり、求愛したり、防衛したりする。境界線上の内と外の相互作用によって、「家」のかたちは変わっていく。ドゥルーズは、自然世界の住人たちが境界上でとる行動の数々を「完全な芸術」だと評している。そして、「文化」という、もう一層の摂理を生きるわたしたち人間にとっての「家」の認知は、人の主な表現方法である「言語」とも深く関係している。
一切の準備をすることなく当日を迎えたわたしは、不思議と不安を感じていなかった。開演時間になり、舞台に上がってみてわかったことは、『NASSIM』という作品が、作家であるナシームの言葉によって紡がれる、彼の記憶のなかの「家」に演者と観客が共に訪問するという構造を取っていることだった。この「家」とは、作家が人生をいきる上で獲得してきた領土でありながら、文字通り彼が帰るべき家族のいる場所を意味している。 この際、やりとりは演者が居住する地域の言葉に訳された台本を介してなされる。わたしが出演した時には日本語の台本が用意されていた。これらの言葉は演者と観客にとっては母国語だが、これは実は作家のナシームがペルシャ語で考えて書いた文章の翻訳である。作家の言葉で書かれていながら彼にとっては異国語で語られる物語であり、演者と観客にとっては異国語で書かれたはずなのに母国語で語られる物語。この二重のねじれが、言語の差異を融かす作用を持っているように感じられた。
演者はどのように台本に従うかということも含めて、事前にいくつかのアドバイスはあるものの、指示らしいものが全くないので、物語をどのように読み進めるかを一任されている。とはいえ、次々と開示される台本の流れを逸脱することはなく、作家の記憶を辿っていると、作家の領土=「家」の輪郭が少しづつ浮き上がってくるのがわかる。すると、いつのまにか演者と観客は、舞台のうえに作家の心象風景が広がるのを見立てている。 演者が台本を事前に知ってはならないとする本作の性質上、これ以上の内容は書けない。重要なのは、この作品が、作家がこれまで築いてきた、もしくは喪ってきた領土=「家」に、演者が主観的に入り込んでいく様子を観客が目撃するという構造をとっていることだ。それはまるで、演者がラビット・ホールに落ち、不思議の国に迷い込んだアリスの心情を抱える様を観客が共時的に体験する、といえばいいだろうか。この時、演者は観客のために/のかわりに舞台に立つ媒介となっている。実際に、舞台上のわたしの驚きは観客にも伝播し、観客の感情がわたしにも戻ってくるのを感じていた。まるで観客というプレーヤーが操作するゲームのキャラクターになったような気もするが、この場合はゲームとは違って演者自身も心をもつ自律的な主体だ。
舞台上で、はじめて出会うナシームからペルシャ語を習うことを通して、わたしはイランという、行ったことのない国の思い出を懐かしく思えた。自分にとっては未知の、他者の記憶に共感し、ノスタルジーを覚えるということ。このことこそが、文学という人間に固有の職能が担ってきた、精神の領土としての「家」をひろげて、異なる「家」同士をつなげるパターンをつくることにほかならない。舞台を降りてからしばらくのあいだ、言葉とはまさに、分ける作用と同時に、結ぶ作用をもつ道具なのだという実感を噛み締めていた。
ドミニク・チェン

ドミニク・チェン
1981年生まれ。フランス国籍。博士(学際情報学)、早稲田大学准教授。クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事、株式会社ディヴィデュアル共同創業者。IPA未踏IT人材育成プログラム・スーパークリエイター認定。2016~2018年度グッドデザイン賞・審査員兼フォーカスイシューディレクター。近著に『謎床:思考が発酵する編集術』(晶文社、松岡正剛との共著)。訳書に『ウェルビーイングの設計論:人がよりよく生きるための情報技術』(BNN新社、渡邊淳司との共同監修)等。
ナシーム・スレイマンプール × ブッシュシアター 『NASSIM』(ナシーム)

| 作・出演 | ナシーム・スレイマンプール |
|---|---|
| 日程 | 11/ 9(Fri) 19:30 塙 宣之(ナイツ) 11/10(Sat) 14:00 丸尾丸一郎(劇団鹿殺し) 11/11(Sun) 14:00 ドミニク・チェン 11/11(Sun) 18:00森山未來 ※追加公演 |
| 会場 | あうるすぽっと |
