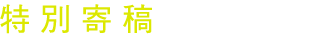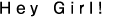藤井慎太郎(早稲田大学准教授)
『Hey Girl!』は2006年11月にパリのフェステイヴァル・ドートンヌの招待作品として、国立オデオン劇場(アトリエ・ベルティエ)で初演された作品である。この作品から、演出に関わる作業はロメオ・カステルッチが一人で手がけるようになった。
女性性と変身のイメージの連鎖
作品には物語と呼べるような物語は存在しない。ロメオ・カステルッチにいわせれば、「誰かが目覚め、立ち上がり、出ていこうと支度をする。出ていく。終わり」というほどの話であり、「直線的であり平面的であり、海に向かって平野を下る川の流れのようなもの」であるという。だが、タイトルにもあるように、少女性あるいは女性性は、この作品の大きな主題である(カステルッチは作品創作に際して、まずタイトルを考え、そこからアイディアとイメージをふくらませていくという)。主役を務めるシルヴィア・コスタの移ろいゆく存在を通じて(誕生から旅立ちまで)、継起するアレゴリー(寓意)的なイメージが描き出され、聖母マリアの受胎告知、(『ロメオとジュリエット』の)ジュリエット、ジャンヌ・ダルクなどの時代や個性を超えた穢れなき女性のイメージが(そうとはっきり示されることなく)繰り広げられ、重ね合わせられる。
美しい悪夢
カステルッチが見せるイメージは、一分の隙もなく構築された絵画や映像のようである(ロバート・ウィルソンのイメージの演劇をもっと極限まで押し進めたものだといってもよいかもしれない)。彼の作品は、額縁(プロセニアム・アーチ)を備えた伝統的な劇場空間のなかで、舞台と客席を明確に分離した上で、観客を寄せつけず、観客のいる世界とはまったく隔たった世界を描き出す。その世界はあまりに美しく崇高でさえあり、だが完全すぎて同時に見る者の不安を掻き立てずにはおかない。アメリカはシカゴ在住のスコット・ギボンズによる音楽もまた、その印象を増幅する。彼の音響世界は、単なる効果音や背景音楽をはるかに超えて、観客の感覚を鋭敏にし、揺さぶり、視覚世界と反響し合ってやはり不安を引き起こす。シルヴィア・コスタは気味の悪い粘着質の液体の中から登場してその美しい身体をさらす。上からつり下げられた円形のガラス板は(太陽や月、あるいは人の眼を思わせる円のモチーフは、カステルッチの作品にしばしば登場する)、次々に砕け散る。完璧すぎる美は不安定で、不気味なものと紙一重であり、はかなくも崩壊を余儀なくされるのだ。
カステルッチのほかの作品と同様、『ヘイ・ガール!』が見せる究極のイリュージョンの世界は、あらゆる観客の脳裏に焼きついて忘れられない経験となるだろう。