対談:森栄喜×山縣良和『A Poet: We See a Rainbow』

私たちは、私たちの虹をみたのだった。同じ虹を、私と、隣にいるだれか、あるいは、もうここにはいない誰かも見上げているのかもしれないと夢想した。去る10月20日からの3日間、昨年の『Family Regained: The Picnic』に続き“まちなかパフォーマンス”シリーズに参加した写真家の森栄喜さんは、『A Poet: We See a Rainbow』と題した今作の根幹にポエトリーリーディングをそえた。全5公演を終えた森さんの表情もまた、虹が垣間見えそうなほど晴れやかだった。
『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・10/21(Sun)南池袋公園 サクラテラス
何とも形容し難い存在感を放つ“白い衣装”に身を包み、書店のギャラリースペース、公園のパブリックテラス、東京芸術劇場前の広場と館内の屋内広場と、性質が異なる複数の環境を舞台に発表された朗読パフォーマンス。書き下ろされた8篇の詩。街中の環境音と、朗読の声を意図的に掻き消すための音楽。開演すると、森さんは“傘”を片手にマイクスタンドに向かって歩いていく。もう片方の手には詩篇が書かれた何枚もの紙を持ち、読み終えたそれは森さんの手から離れ、ひらりと床に吸い寄せられていく。パフォーマンスの最中、とある道行く人は吸い寄せられるように足を止め、ある人は“無関心”の様子でその場を通り過ぎて行く。偶然性を内包した時間と空間——この作品に対峙する方法は、人の数だけあった。
長く降り続けた雨が上がり、青い空が顔を見せるかのように、音楽がわずかに転調した。どうやら『息子たちへ』という詩が読まれている。隣に座る人は、断片的に聴こえる言葉を手掛かりに詩篇がプリントされた紙を目で追っている。違う人は、立ち尽くし、繰り返し深い相槌を打っている。きっとこのパフォーマンスは、受け手によって自由に解釈されていく。だからこそ、森さんの声に向かって、どうしても耳を澄ますことだけはやめてはならない気がしていた。
声が掻き消される朗読パフォーマンスはどのようにして生まれたのか? 綴られた詩と、話者を包み込んだ衣装に込められていることとは何か? 最終公演を終えた森さんと、衣装を手がけた〈writtenafterwards〉のデザイナー山縣良和さんの対談は、昨年のクリスマスイブに行われた朗読パフォーマンスの回想から始まった。

森:12月24日の夜に、僕が所属するギャラリーで「Family Regained」に関連するパフォーマンスを行うことが急きょ決まったのです。そして遠い時代の、亡くなったセクシャルマイノリティーの恋人たちに贈る“鎮魂歌”のような作品をつくりたくて、すぐに4篇の詩を書き、ベルを鳴らしながら朗読しようと。ベルの音には弔いの思いが込められていて、本来は僕たちの存在を知らしめるはずなのに、その音で僕の声がかき消されてしまうという矛盾。その状況は、“声”が届きにくい世界にある人々の意識や社会環境を暗示させるし、僕が抱いている「どうしようもなさ」のようなものも宿っている。このアプローチが、今回の“まちなかパフォーマンス”と地続きに繋がっていったんです。そもそも 既に街中には僕の声を邪魔し、消そうとする騒音がある。物理的な車が走る音も、四方から聴こえる人々の声もそう。そうした環境下で発表する『A Poet: We See a Rainbow』では、意図的に音楽を付け加え、日常空間よりさらに声が 聞こえない環境をあえて設定することにしたんです。それは、僕が常日頃から感じている“声が届かない”実際の現状と、その悲しさを、観る人に伝える手段でもあった。
——掻き消されるという事実がかえって、何かが確かに存在していることを明らかにしているように思えました。
森:そうですね。面白かったのは、パフォーマンスの内容も詩も全会場で同じなのに、場所によって意味合いが変化したこと。不特定多数の人が行き交う路上や、家族連れがビニールシートをひいて休日を過ごしているような芝生がある公園。会場によっては 本来は掻き消すための音が、人を引き寄せてもいた。妨害するための演出によって、僕の存在が可視化されていったんです。

山縣:逆説的なことが同時に起こったわけですね。その音と声が、時と場所の違いだけでなく、受け取る人の気持ち次第で何にでも変容する可能性を持っていたと。今の話を聴いていて“装う”という観点でのパラドックス的な部分を思い出しました。例えばマスク。自分を隠すためのものだけど、逆に、隠している“そのもの”を顕にする側面もある。覆うことで晒されるというか、隠されることで何かが内側から出てくる、投下されるような感覚はあると思うんですよね。
森:確かに今回、“隠すこと”は重要でした。身に纏うものも、ジェンダーや体型だけでなく、時代性も隠れていた 。一方で、隠しているからこそ、どんどんとあらわになってしまう何かが溢れ出したのも事実で、そこは本当に面白かったなと思っています。パフォーマンス中は、言葉も隠されたわけですから。
 『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・10/22(Mon)東京芸術劇場 劇場前広場
『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・10/22(Mon)東京芸術劇場 劇場前広場
——音によって“隠された”8篇の詩の内容は、半自伝的でもあるとのことでしたね。
森:そうですね。歴史的な事実もあれば、僕の目の前で起こったことや、ふと思ったことなど。読んでいただくとわかるんですけど、本当に些細なことを綴っているんですね。例えば“メントスを一個もらった”ときの思い出だとか。今回朗読した導入的な詩の中に“ヘアピンが 落ちる音 1969年”というのがあるんですが、これはニューヨークの〈ストーンウォール・イン〉というゲイバーに警察の不当な強制捜査が入って初めて抗議の暴動が起こり、その出来事からレインボーパレードが始まったという“反乱”に基づいているんです。ドラァグクイーンの人が激昂して、最初に警察官にヘアピンを投げたのがきっかけで暴動が始まったという逸話も残っていて。たったひとつのヘアピンが警官に当たって床に落ちる音が響き渡り、変わった歴史があるって奇跡的だなと思って。ヘアピンの話自体は、伝説のようなものかもしれないけれど、でもこの反乱がきっかけで人々の意識が変わり、今日に続く権利獲得への運動につながっているのは確かで。
山縣:なるほど。そのあとの“繰り返す しゃっくり”というのは?
森:“ヘアピンが落ちる音”のような革命的な変化のきっかけがもっと繰り返されてほしいという僕自身の願いと、まだまだ 繰り返さなくてはいけない社会的状況を、しゃっくりに例えたんです。僕は 作品の中で、社会や時代、人の意識だとか、 大きなスケールのなかに、普段のささやかな“気付き”を投げ込むのが、すごく快感なんです。
山縣:快感というと?
森:その1ミリの気付きが、壮大に構築されていた世界を破壊していくかもしれない。そして、真っさらになって新しく生まれ変わるみたいな感覚。実は、山縣さんが“魔女”をテーマにした2019年春夏コレクションの展示会を見に行ったときも同じようなことを思ったんです。インスタレーションのなかで、歴史的にもかなり複層的な意味がある“魔女”が、洗濯を干していたり、アイロンをかけていたりしていた。スケールがまったく違うものを一つの世界に閉じ込めている感覚。もしそうじゃなくて、スケールが大きい言葉を、同じくスケールが大きい装飾や演出で見せると塊のようなパワーが発生するかもしれないけど、受け手側に負担になるというか。そこに“普段”というスケールを組み合わせる理由があるのかなって。
山縣:たしかに僕もそういう思考性はありますね。コレクションも、時代を超越した大きなテーマに関心が向きがちです。けど、どこかに親近感をつくったり、身近なものを取り入れたりしながら“突っ込みどころ”をわざと入れたりするんです。壮大なままにしない。言い方を変えれば、崇高になることの拒否は意識していますね。そもそも特定の答えを作りたくないというのがあって、ものづくりの過程で一つの答えにたどり着いた瞬間に、どこかに突っ込みどころがあるのではないかという発想が出てくる。それは“解釈”を見てもらう方に任せたいという意思だし、そこに宝物もあれば、ゴミもあるという、価値のヒエラルキーすら、ぐちゃぐちゃになっている状態が理想的だなと常々思っています。栄喜さんの作品には、いろいろなものが散りばめられていて、たくさんの引っかかりがある。それらが見る人によって、意味にも、無意味にもなるというか。きっと受け手側のコンディションによっても、詩のフレーズの入り方、言葉がどのようにコラージュされていくかが違うんだろうなと。
森:そうですね。僕自身が写真を撮り続けていて気づいたのは、嘘がまったく含まれていない“本当のこと”を偽らずに写し出すと、本当っぽくならないということ。本当のことって実は、断片的過ぎたり、無秩序な順序だったりするじゃないですか。 “本当”のまま描くと、 かえってすごく抽象的にも、フィクションのようにもなると思っていて。 それでも作品に触れると何かがすっと入ってくるというのは “本当のこと”だからだと思うんです。
 『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・10/21(Sun)南池袋公園 サクラテラス
『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・10/21(Sun)南池袋公園 サクラテラス
——森さんは昨年末の朗読パフォーマンス、『読書人』での連載小説「Letter to My Son」、そして今回と、テキストを認めることをされていますが、写真作品と連なっている部分はどういうところですか?
森:僕の文章って、何かへの訴えや感情の表現というよりは、基本的に“描写”なんです。「書く」ことは確かに新しい挑戦ですけど、実は、使っている感覚 は写真撮るときと同じなんだと気づいた。 だから、やっぱり僕の“世界を見る”手段というのはここなんだと再確認していて。
山縣:話を聞いていて思いました。見方は同じで、それを表現するメディアが言葉であるか、写真であるかという違いなんですね。僕の場合、一番表現したいところは結局、"ファッションの愛おしさ"であり、ファッションそのものが否応にも人間味が溢れて出てしまっているものだからです。作り手としての嗜好性は当然ありますけど、時に超ダサいものも、ある意味それすらも愛おしいなと思える瞬間がある。いいとされるものも、悪いとされるものも一旦バラバラになって、たくさんの“答え”を想起できればできるほど嬉しくなっちゃうみたいなところがあるんです。ただ、ファッションのリアルな話ではビジネスがある。だから本当に難しくて、常に葛藤があるんです。いわゆる“限定的で、分かりやすい答え”があるほうが、ファッションビジネス的にはいいとされているので、様々な方にどのように価値観を受け入れてもらうか常に試行錯誤です。
森:僕は山縣さんの服って、強制力が皆無だと思うんですよね。他のデザイナーさんの中には、理想とする形で纏ってほしいという願望が強い服もたくさんあるじゃないですか。そういう“提案”って、かなりやりやすいし、広まりやすい。その反面、“問いかける”ものは、時に“分かりにくさ”を伴うから問われる側の体力や時間を必要としてしまう。僕の今回のパフォーマンスも結局、詩の内容そのものではなく、どう繋がりたいのかという話なのかも。詩の言葉一つひとつをしっかり理解してつながりたいのか。あるいは、ただその場にいるだけでつながると思えば、別に言葉とか関係ない。公演を終えて、究極は、そこに共にいることそれだけでいいんじゃないかという感覚も生まれてきたんですよね。
山縣:よくわかります。栄喜さんのパフォーマンス中、詩が書かれたプリントを読んでいる人もいれば、じっと栄喜さんのことを見ている人もいた。その場にはいるけど、それぞれが違う方向を向いている感じ。そこで、たまたま出会ったもの同士がハレーションのようなものを起こしたときに、何かが劇的に変容する瞬間があるのは確かだなと思うんです。僕はよく“Fashion is not static state, dynamic phenomenon(ファッションは留まるものでなく、ダイナミックな現象である)”と言うんです。人が変わり、環境も変われば、当然違うものが生まれる。少なくともファッションは、決して固定化された塊ではなく、常に流動するものなんです。
——衣装について詳しくうかがっていきたいのですが、森さんは山縣さんに依頼する以前、何か想定していることはありましたか?
森:今回の詩が、実はおじいちゃん、青年、少年 という三世代の視点が織り交ぜられているんですね。時代も交錯していて、都市もニューヨークだったり、東京だったり。年齢やセクシャリティー、階級、国籍といった 様々なことが密度濃く過剰に詰め込まれている世界。だから、先ほどの“提案”の話にもなりますが、身に纏うもので、ある特定されたイメージを「こうみてください」と受け手側に発信することをすべて排除したかった。
——最初にどのような依頼の仕方をしたのですか? ギルバート・ベイカーがデザインしたレインボーフラッグの簡潔な歴史、ジャン・コクトーやピエル・パオロ・パゾリーニらの詩篇を共有されたと。
森:そうですね。まだ詩は書き上げていなかったし、音楽も完成していない。だから、山縣さんにはいくつかのキーワードと今回のコンセプトと同じ世界観がある詩の一節を伝えただけでしたね。

山縣:僕の発想の仕方として何個かのフレーズをもらったら、それらから連想して、ストーリーを膨らませていく癖があるんですね。虹が出るのって、雨が降って、晴れ間が生まれたとき。僕のイメージのひとつに『北風と太陽』の話もあったので、気候の変化が絶対に起こっているし、もし雨が降っているならレインコートでフードは必要だなとか。その一方で、僕がいま最も興味を注いでいる“魔女”のイメージとも重なりますが、服飾史のなかでも重要な役割がある“ベールに包まれて隠される”ディテールも同時に湧いてきた。謎めいているものに対して人は何かを感じやすいから。でもやっぱり、雨が降っているのなら“傘”が必要だと……
森:そうそう。僕は一言も傘が欲しいとか言っていなかったんですね。今回のパフォーマンスを、投げかけたキーワードを組み合わせて “光景”としてみてくれたからこそ、傘が必要だと気がついてくれたんだと思うんです。そういう衣装デザインのスケールの捉え方に本当に感激したんですね。
山縣:それこそ僕もまったく想定してなかったことで、布地でできたあの傘を、朗読の後半にひっくり返したじゃないですか。衣装としても象徴的なビジュアルの変化が起こって、ちょっと魔法がかかったみたいな造形になって。ここに新しいストーリーや、何かのメタファーが偶然にも生まれている感じが面白いなと思ったんですけど、あれって意図的に?
森:あの変化を見つけたのは偶然なんですよ。もし傘を置いたら、とか色々試しているうちに。ただ、傘が、傘じゃないものに変容することの解釈が実はまだ追いついていないんですよね。本当にいろいろな見方ができる と思うし、それが良いと思っています。あと、音に掻き消されて聴くことのできなかった詩の内容を一枚の紙にして配布したんですけど、そのドローイングも山縣さんにお願いしたんですよね。
山縣:用途だけの、すごくサラッとした依頼でしたよね。最初は、クレヨンか色鉛筆で描こうかと思ったんだけど。
森:僕もそうくるだろうなと。
山縣:うん。ただ、一回やってみて、なんか違うなって。それでやっぱり雨だな、濡れている感じだなと。それで画材を変えて水彩でやってみたんです。でも、乾いてからスキャンするとやっぱり違う。まだ絵の具が紙に染み込んでいない、潤いがあって、瑞々しい状態が一番綺麗だなと思い至って。水をたっぷり入れて描き直したものを天然光で写真を撮ろうとしたら、偶然にも本当に雨が降ってきたんですよ。
森:じゃ、この滲みとか、きっと雨粒の跡かな。
山縣:もうどれが雨粒の跡かはわからないんですけどね。あと、この薄い紙の素材は想像していなかったし、ひっくり返して透けるというのもとても良いなと思って。今回、キャッチボールはあったけど、綿密にすり合わせるのではなく、解釈し合うみたいな感じだった。
森:うん。必要最小限で進めました。
山縣:やりとりに“間”があったからできたのかもしれない。僕は勝手にレインボーと雨を合体させて、傘のイメージを持ってきて、ストーリーを編んだ。その解釈を栄喜さんは許してくれるだろうという理由のない確信もあったんですよね。
森:さっきの話と繋がるんですけど、“提案”だと、少しのズレだけでも 全体がぼやけてしまう。虹を見るシチュエーションとまったく同じで、今回は、ここから見てください 、こういう虹がきれいです、という“提案”ではない。それぞれがまっすぐに 虹を見上げてさえしていれば、成立するプロジェクトだと強く感じていたので。

『A Poet: We See a Rainbow』公演写真・東京芸術劇場 ロワ広場
——最後に、お互いにシンパシーを感じる部分についてお聞かせいただけますか。
山縣:作品が、いつも栄喜さんと共に歩んでいるんだということをすごく感じています。当時のパートナーとの生活があって、家族があって。個人的なイメージでいえば、最初の空気感は澄み切ったブルーに近い感覚だったんですが、それが赤に変化し、また違う家族像が出てきた。そして今回はレインボー。また一歩踏み込んでいて、老人から少年、青年と違うストーリーが生まれているんだなと。僕はそうした栄喜さん自身の“歩み”にすごく親近感が湧くし、先ほど「全部が“本当のこと”」と言っていた意味がひしひしと伝わってくる。ジャンルは問わず、僕はそういう作者が好きだし、共鳴するんです。ひるがえると、僕自身ももっと“歩みたい”という感覚がある。ファッションは若い人のものだという考えが嫌だし、それに基づいてしまうと僕らが特定の年齢から離れていけばいくほど疲弊してしまう。ファッションは、そもそも全ての人に対して根源的なもので、切っても切れないものだと僕は考えています。だからこそ歳を重ねて、作り手の成長とともに変わっていく。ファッションの表現もそうありたいと思っているんです。
森:同じ感覚を持っているんだなって思いましたね。そもそも今回の衣装を依頼するにあたって、山縣さんが今一番興味があって、コレクションで探求しているフィールドの影響は、絶対に受けると思っていたんですね。それで“魔女”の展示会を見て、今回のプロジェクトや僕が抱いていたコンセプトと馴染むと直感したし、例えば「過去のコレクションのこの風で作ってください」と伝えたら、きっと山縣さんはしらける。今集中している世界があって、過去には戻らない、逆行しないタイプというか。大きな流れでのなかで、この企画だけ僕がちょっと一緒に添わせてもらう。そんな感覚なんです。だから、最小限のやりとりでしたけど、本当に“魔女”のコレクションの延長線できてくれたから良かった、嬉しかったんです。効率的に薪を買うんじゃなくて、山縣さんという木の枝を借りる感じ。僕は、その枝同士が繋がっているんだなと思えたんです。
写真家 森 栄喜
 Photo by Shun Wakui
Photo by Shun Wakui1976年石川県生まれ。2014年『intimacy』で、第39回木村伊兵衛写真賞を受賞。『tokyo boy alone』(2011)、『Family Regained』(2017)などの作品集のほか、同性婚をテーマにしたパフォーマンス『Wedding Politics』(2013-2016)がある。F/T17では新しい家族の形を提示した映像作品『Family Regained: The Picnic』を池袋西口公園、豊島区庁舎で上映した。
衣裳デザイナー 山縣 良和

writtenafterwards デザイナー・coconogacco 代表 2005年セントラル・セント・マーチンズ美術大学を卒業。在学中にジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。2007年にリトゥンアフターワーズを設立。2008年より東京コレクションに参加。2014年に毎日ファッション大賞特別賞を受賞。2015年には日本人として初めてLVMHプライズのセミファイナリストにも選出された。またファッション表現の研究、学びの場として、2008年より「ここのがっこう」を主宰。
まちなかパフォーマンスシリーズ
A Poet: We See a Rainbow
(ア・ポエット:ウィー・シー・ア・レインボー)
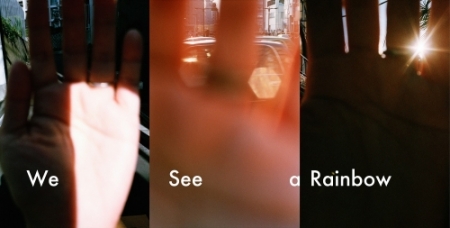
| 作・演出・出演 | 森 栄喜 |
|---|---|
| 日程 | 10/20(Sat)17:00 / 20:00 ※予約優先 10/21(Sun)15:00 10/22(Mon)15:30 / 18:00 |
| 会場 | 10/20(Sat)ジュンク堂書店 池袋本店 9階ギャラリースペース 10/21(Sun)南池袋公園 サクラテラス 10/22(Mon)東京芸術劇場 劇場前広場 / 東京芸術劇場 ロワー広場 |