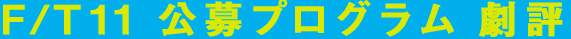灼熱の娯楽を目指して (『バナ学バトル★☆熱血スポ魂秋の大運動会!!!!!』)
<福嶋亮大>
劇場に足を運ぶ直前に、この「バナ学バトル★☆熱血スポ魂秋の大運動会!!!!!」予告編の動画を見たときには、「ライトオタクがニコ動のMAD的なハチャメチャさを演劇に取り込んでみた」という程度の作品かと思って、実はたいして期待していなかった。その選曲やセリフは明らかに、今や日本のポップカルチャーの一大センターと呼ぶべきニコニコ動画の影響下にあったからだ。だが、その予想は完全に間違っていたとは言わないまでも、実物はそれ以上の何かであった。
そもそも、F/Tの公募プログラムに名を連ねていると言っても、この作品はふつうの意味での演劇ではない。そこにはもはや、役者の中途半端な演技は一切存在しない。スクール水着や制服姿の女の子がドラムを叩き、女装したマッチョがパンツ丸出しで逆立ちし、涼宮ハルヒに扮した二階堂瞳子が熱唱するその舞台は、ほとんどコスプレイヤーたちのどんちゃん騒ぎと呼んだほうが実情に近いだろう。とりわけ、大勢の異形の役者=コスプレイヤーたちがアニソンを絶叫しながら、舞台狭しと激しく踊る光景は、まさに観客の度肝を抜くものだ。それだけではない。水やキャベツやワカメ(?)の切れ端から、役者の衣裳、果てはサイリウムまで大量の物体が次から次へと客席に投げ込まれることによって、会場全体が狂騒に包み込まれていく......。このように、バナナ学園純情乙女組はまさにノンストップで、異常な熱量に満ちた「大運動会」を繰り広げる。このパフォーマンスだけは、ライブで体験しなければ何も分からないだろう。ということは、ある意味では批評不可能ということでもある。
ゆえに、議論をいったん作品の外側に拡張しておこう。もっとも、僕は別に演劇批評の専門家ではないし、まじめに日本の演劇を見始めたのはたかだかここ二年ほどのことにすぎない。その限界を踏まえた上であえて言えば、昨今の若者演劇の中心的関心は、社会に対するメッセージではなく、演劇史への応答でもなく、ずばり「感情移入」にあると思われる。去年個人的に見た作品で言えば、たとえばマームとジプシー『ハロースクール、バイバイ』や快快『Y時のはなし』などがその筆頭だろう。青春ドラマを売りにするこれらの作品は、意地悪な見方をすれば、ほとんど高校生演劇の延長のように思えなくもない。だが、仮に観客を引き込み、笑わせ、涙を流させるのが演劇の使命であるならば、等身大の若者が健気に頑張る高校生演劇タイプの作風が選ばれるのは、ある意味では合理的である。
だが、こうした風潮に対して、バナナ学園純情乙女組の作品はもはや高校生演劇的ですらなく、文字通り「運動会」さながらのハチャメチャな世界に突入している。こうなると、観客は舞台上の役者に感情移入するどころではない。実際、水しぶきをあちこちで吹きかけ、観客の頭上に野菜やら何やらの謎の物体を投げ込み、アニソンやAKBの楽曲の轟音を響き渡らせるこの作品の観賞は、ひとによっては苦行そのものだろう。しかし、このカオティックで攻撃的な祝祭空間は、間違いなく感情移入の演劇を破壊している。言い換えれば、役者を(あるいは観客を)別の人格に成り代わらせる「演劇」(再現前)ではなく、舞台そのものをじかに体験させる「パフォーマンス」(現前)が、日本のポップカルチャーの素材を借りて再起動されているのである。
むろん、カオスをカオスとして見せるのは決して簡単なことではない。たんなるアナーキーな暴走では、観客は興醒めする一方だろう。その観点からすれば、この作品はむしろ「計算されたカオス」あるいは「統御されたどんちゃん騒ぎ」によって満たされていたと言うべきである(もとより、理知の拘束をかなぐり捨てるためにこそ、作り手は理知的に計算するものではなかったか?)。振り付け、選曲、MC、緩急の配分、間合い、そのすべてにわたってどんちゃん騒ぎを効果的に出現させるテクニックが駆使されていたことは、ここで是非とも指摘しておかねばならない。
作中で大量に動員される日本のポップカルチャーも、必ずしもこの劇団の趣味だけから来るものではない。彼女らは、ニコニコ動画をはじめ日本のポップカルチャーのカオスを表面的に真似したというよりも、逆にカオスの熱量をとことん増すために、いわば方法としてポップカルチャーを用いたと考えたほうがよいだろう。実際、たとえばオタクのアニソンは今やポップスを侵食し、ライブを侵食しているが、それはアニソンが一切の恥や衒いを忘れさせ、歌い手と観客を共通のノリに導くことができるからである。あえておかしな言い方をすれば、オタク文化が得意とするのは、いわば「純度の高い混沌」なのだ。バナナ学園純情乙女組は、そうした最近の日本文化を確かにツールとしてうまく生かしていたと言えるだろう。
いずれにせよ、演劇批評の側からは、バナナ学園純情乙女組のパフォーマンスに対して当然賛否両論があるに違いない。とはいえ、僕の考えでは、この劇団を演劇の枠内でだけ解釈するのは、彼女らの選んだ「戦場」を見誤っている。おそらく彼女らがやろうとしているのは、演劇界を良くするとか、演劇を通じて社会に問題提起をするとか、そういうことではまったくない。むしろ彼女らのライバルは、現代日本を満たすすべての娯楽だと言うべきだろう。それこそ、ニコニコ動画やAKBのライブすら凌駕するような灼熱の娯楽を目指すこと、ほとんど開き直りに近いこのシンプルな原則が、作品の「謎の感動」を支えているように思われる。逆に、「ポスト震災の時代に演劇に何が可能か」という類のまじめな、そしてまたいささか優等生的な題目は、この作品において完全に粉砕されている。世界に天災が起ころうが起こるまいが、とにかく今この舞台で、常識を超えた何らかの衝撃的体験を観客に与えなければ、表現は死ぬのだ。そして、狭い意味での演劇を捨てて、娯楽に徹しているがゆえに、かえって劇場でしか体験できない何かがそこに現れていることも確かなのだ。
ただし、僕個人の見解を率直に言えば、こうした運動会さながらの即自的なパフォーマンスは決して理想的だとは思わない。そもそも、演劇を含めた芸術一般の役割とは、私たちの文化的遺産に対して検針を下ろし、その内容を問い直すこと、それによって自己の、あるいは他者の尊厳と理解のベースを不断に作り替えていくことにあるのではなかったか?ベンヤミンふうのレトリックを使えば、芸術というのは、世界の諸事象に対して新しいやり方で反応するための「警報機」に近いものだ。確かに、多くの観客はバナナ学園純情乙女組のパフォーマンスにその場では圧倒されるだろう。だが、僕に言わせれば、それは自己や他者についての理解のあり方を本質的には変えるものではない。言い換えれば、世界に対する鋭敏さを養う警報機ではないのである。
しかし、バナナ学園純情乙女組に、こうした批評家的な物言いをあっさり粉砕する迫力と熱量があったことも否定できない。それに、どのみち彼女らは、こうした批評はとうに織り込み済みだろう。彼女らは、演劇を介して何かを表現するよりも、そうした迂回なしにパフォーマンスそれ自体のインパクトを脇目もふらずに高めることを選ぶ。実際、たとえば中途半端に震災をネタにするくらいならば、いっそそんな拘束を潔くかなぐり捨ててしまったほうが、表現者としての倫理と責任にかなっていると言えないこともないだろう。とにかく、これまで他のどのジャンルにも存在しなかった最強のエンターテインメントを一直線に目指すこと、そのために手持ちのテクニックと素材を惜しみなくつぎ込むこと。繰り返せば、彼女らにとって、競争相手はもはや狭い演劇業界ではなく、おそらく社会を満たすすべての娯楽なのである。この無謀なまでの潔さが存在する限り、バナナ学園純情乙女組はこれからも支持され続けるに違いない。
- バナナ学園純情乙女組
- 2011年12月01日