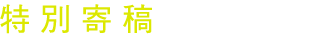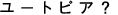『ユートピア?』
サラ・ヤンセン (評論家・研究家、在ブリュッセル)
世界規模の金融恐慌・経済危機、拡大し続ける格差、軍事紛争の多発化、ナショナリズムの増長と社会の右傾化など、重要な問題を様々に抱える今日において、「ユートピア」という概念に触れるとき、我々は驚異の念を抱くだろう。実際近年の演劇作品のメインテーマとして、これらの危機的情況を目にすることが多いように思われる。舞台芸術においては、かなり暗い世界観を描くものが多く、アーティストは過去の理想主義的な概念、すなわちユートピア的概念の崩壊や精神文明レベルでの危機に果敢に取り組んでいる。その状況の中で、『ユートピア?』という作品では、世界の異なる地域から刺激的なアーティストを集めることによって、今日我々にとって複雑となっているこの概念の意味を追求し、ユートピア的演劇を探る事が目指されているのである。
フランス・ブザンソン国立演劇センター芸術監督であるシルヴァン・モーリスが、非常に異なるコンテクスト、文化的背景において活躍する二人の劇作家・演出家、平田オリザ(日本)とアミール・レザ・コヘスタニ(イラン)にアプローチしたのは、数年前のことだった。40分間で日・仏・イランそれぞれ3名ずつの俳優により多言語で展開される作品を書いて演出してもらうことがねらいである。こうして発した刺激に満ちた出会いを機とし、『ユートピア?』という作品を通じて今日のトピックに対しての三者三様のアプローチ、あるいは対照をなす三つの見解が表されようとしている。
平田オリザによって作・演出される『クリスマス・イン・テヘラン』は、テヘランの郊外のスキーリゾートを舞台に、日本とフランスからやってきたホテル経営者とイラン人のスタッフがアメリカ企業に見放され、倒産寸前のホテルの再建に奮闘するという筋だ。クリスマスをきっかけにホテルを取り巻く人々の間で文化的・宗教的差異が顕在化してくる。一方アミール・レザ・コヘスタニが作・演出する作品では、この平田作品の裏側、つまり平田の芝居が上演されている間に楽屋で起こっていることを描写するような演出となり、私たちが既に観た芝居をもう一度違う側面から観直すと言う事になる。この二つの作品はモーリスの演出によるプロローグとエピローグという枠組みに収められることにより、興味深い演劇作品になるだろう。
平田オリザは、自分自身の作品だけではなく、演劇全体を通して、「対話」(舞台上だけではなく、戯曲とその文脈や背景において)の重要性を多く語り、今まで二言語演劇の様々な可能性を探ってきた。『ユートピア?』において、更に次の段階へと発展していく。『クリスマス・イン・テヘラン』では俳優各人はそれぞれ自分の母語で話し、このことが人物間のやりとりを相当複雑化していくだろう。コヘスタニの作品では、楽屋という設定において、会話は少なくなり、更に曖昧に抽象的に構成されていき、コミュニケーションはもっと決裂していくと考えられる。
このように、このプロジェクトはまず最初の時点から、多文化的・多言語的な対話が本来的に抱く問題やリスクを取り組んでいる。と言うのは、多文化的・多言語的な対話の複雑性を避けるのではなく、複雑さこそがテキストの構成に織り込まれているからだ。『ユートピア?』はこれらの問題にまっこうから向き合い、それらを公平にプロジェクトの中心にすえている。
平田オリザは演劇を内部から変革していくことが可能であると確信している。欧米や日本の本来の実験的演劇は演劇の決まりごとを解体して、それをまったくゼロから創りなおす必要があると感じていた。それに対して、平田の「現代口語演劇」は日本近代演劇の要素を保ちながら、演劇を内部からラディカルに書き直したものである。『ユートピア?』も同様に、国際共同企画における変革の道を歩もうとしている。「今まで、国際共同事業というのは、仲良くするか、あるいは対立を描くかと思います。アミールともこの点について数多く話してきました。イランは我々がよく知らない国ですが、結構普通に生きているところもあります。そういうところを描きたいと思っています。」と平田は語る。(i)
平田オリザの創造する劇世界は我々の日常生活のリアリティーと大変似かよっている。しかしながらそのリアルさが奇妙に感じられるものでもある。微妙に何かがズレている。日仏二ヶ国語の演劇、『別れの唄』(2006)を平田と共同制作したロラン・グットマンは、自身が平田オリザ作『S高原から』(2004)を演出した際、当初戯曲の持つ文脈から反れ、エキゾチシズムに走ってしまわないようにと懸念していたが、その居場所がないような、ある種の疎外感のような感覚が戯曲に組み入れられていることに気がついた。(ii)平田の描くミクロコスモスは、実世界、とりわけそのイーブンではない力関係に起因する人間関係を映し出しているのである。その一方で彼が描く人物たちは世界から隔離されているようにも見える。彼らは周囲と繋がったり、積極的に関わったりすることはしないのだ。
アミール・レザ・コヘスタニに多くの賞賛をもたらした『Dances on Glasses』(2001)では、二つのまったく異質な世界から来た少年と少女のストーリーが語られ、その距離は埋めることができず、「激しくて、生々しい感情を生み出す」スタイルで描かれている。(iii)国際的フェスティバルを席巻している今シーズンの新作『Quartet: A Journey to the North』でも、人々の距離感やコミュニケーションの欠如が重要なテーマとなっている。『Quartet』の中で、コヘスタニはこの距離感を強調させ、感じせる為に、日常的な言語やドキュメンタリー的要素を非現実的な設定と対比させて見せている。俳優がお互いに背を向けた状態、カメラに対峙するという状態で、ダイレクトなコミュニケーションを避けながらモノローグを発する。観客は舞台の四辺に座っているので実際には自分の正面にいる俳優の顔しか見えず、他の俳優たちはスクリーンに映し出される。このような観客と俳優達との遮断された関係もあいまって、効果は倍増する。
これらの作品では、理想的でパーフェクトな状態の未来よりも、我々が実生活で日々体験していることにずっと近いものを描いている。つまり我々のコミュニケーションの根底にある身ぶり、言いよどみや沈黙(無言)が含まれている日常会話でそういう状況を描いているのだ。目だったアクションが少なく、(確かに両演出家の作品では俳優は座っている場面が多い)物語があまり展開せず、いくつかのストーリーが時々交錯し、その筋は徐々にしか見えてこない。それはアーティストにとってのリアリティを提示し、我々が向き合っている世界の乱雑さを示しているのである。観客は舞台上の世界が、我々の世界とまるで繋がっているかのように、そこに引きこまれていく。パフォーマンスは結果的にきわめて静かで繊細である様でもあり、一方で対峙的で強烈様である様でもある。いずれにしても我々はこの作品を観て、観る前と同じ自分ではいられないのである。
両者の作品は現実の世界に根ざしていながらも、同時にそれを問い直し、覆し、変化させていく。その点で彼らの作品は、ミシェル・フーコーが「ヘテロトピア」と名づけた概念との関係が頭に浮かぶ。フーコーにおいての「ヘテロトピア」は「ユートピア」と違って、或る文化に属するリアルな場所を再生又は再設定する実際に存在する場所や空間である。
『ユートピア?』に関わっている演出家のうち、誰1人として以前楽観視やユートピア的な作品を作ったことで知られている訳ではない。平田は「作品をどう捉えるかによる」と言う。「世界の見方に関しては非常にシニカルなところはあるとは思いますが、一方で全く希望がないかとそうでもないです。そういう世界のなかでどういう風に一日一日を生きているかを考えているともりです。決してその世界に対して楽観的にはなりません。しかし努力をすれば何かが改善するとかそのようの近代主義、進歩的な世界観は全く持っていません。私たちはどうにかして生きていかなければならないわけです。シニカルではあるが、ニヒリズムではないと思っています。」(iv)
『ユートピア?』に関わっているアーティストはそれぞれまったく異なったバックグラウンドをもっていながらも同じテーマに関心を示している。3人とも微妙な文化の違いに興味を持ちながら、グロ-バルな、普遍的な問題を取り上げている。異なったアプローチや多言語的視点を結びつける過程では類似点と相違点が浮き出され、その中から、自分のもつ文化への新しい視線、新しい読み方、書き方が見出されていく。演劇はこういった微妙な違いを顕在化させる上で、大変重要で効果的な役割を担う芸術だ。
平田は、外国でコミュニケーションを取ることにはいつも困難が付きまとうが、成功したらとても楽しく愉快だと話す。彼らの新作『ユートピア?』では異なる文化や言語間でコミュニケーションの難しさ同様、楽しさを感じさせられれば、と考えているそうだ。ロラン・バルトは『表徴の帝国』において、日本語及び日本文化について観測しえた要素を統合し、そこから新しい「日本」と呼ぶシステムを構成している。そこでは、「日本」は実際の日本国民ではなく、架空の空間、ユートピアのようなものだ。バルトは自分がなれている象徴的システム以外のシステムが存在することが、システムの相違の発見するのに効果的だと言う。「きわめて遠い外国語が微かな光によって、わたしたちに暗示することのできる抜きがたい断絶の姿、そのなかに身体ぐるみ運びこまれるのは、なとありがたいことか。」(v) こういう異文化コミュニケーションへ積極的なアプローチを間違いなく、『ユートピア?』において我々は眼にすることになるだろう。
i サラ・ヤンセンによる平田オリザへのインタビュー (2008年10月、ブリュッセル市にて)
ii Laurent Gutmanによる平田オリザへのインタビュー (2002年10月、東京にて) www.theatre-contemporain.netに掲載。
iii J.L. Perrier、「Amir Reza Koohestani, 25 ans, dramaturge à Chiraz」、Le Monde に掲載(2004年)
iv サラ・ヤンセンによる平田オリザへのインタビュー (2008年10月、ブリュッセル市にて)
v ロラン・バルト 「表徴の帝国」、宗佐近訳、ちくま学芸文庫、16ページ。