

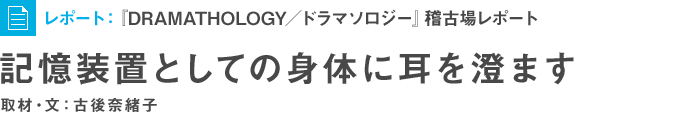
伊丹市の公共劇場が力を注ぐ分野で嘱望される27歳の演出家と、70歳以上の地域住民。アイホールの「地域とつくる舞台シリーズ」の第1弾が結びつけた両者は、その組み合わせの意外性以上に、出演者家族や友人と演劇関係者、両サークルの価値観を揺さぶる驚きを初演でもたらした。再演という機会を得たことで、彼らの取り組みはどのように深化しているのだろうか。初顔合わせから2年、初演から1年半近くを経て、再開された稽古場に取材した。
「再演と聞いたとき、これが演劇だということを、こういうかたちで認めてくれたのかなって思いました。演劇っていったら、台本があって、台詞を覚えてっていうのばかりしか知らなかったから、こういう作品を認めてくれる世界があるんやなって思いました」(相馬)
「びっくりしました。このメンバーが集まったことにも縁を感じるようになっていたので、初演が終わった後もまた集まれたらとは思っていましたが。ただ、伊丹の人と作った伊丹の話が、東京でどんなふうに受けとめられるのかは少し心配です」(飯田)
出演者たちから聞かれたのは、何より再び集まることができた喜びと、想定外の筋から評価を受けた驚き。そして、地元を出て未知のお客さんの前で上演するという自覚から新たに生まれた緊張感や責任感だ。
「夢にも思っていなかったけど、また招集いただいて......。これもいいチャンスなんかなと、挑戦したいけどやれるかなと、自問自答しながら来ています。慣れに走らないようにせんと、相模さんや携わってはる方の責任もある。慣れは怖いと思いました」(足立一子)

稽古では具体的に、初演で決まった場面について、一つ一つの所作を捉え直す作業が進められている。かなり細かい指示と説明がなされるが、それらは演技を固める方向のものではないようだ。演出の相模は「揺らいでいるほうがいい」と言う。
「見る側も、"こなれた素人"に出てこられても困るというか......(笑)。みんなが颯爽と出てきて、読むのも超うまい、『えらい慣れとんな』となるより、ある程度失敗するかも知れないという危うさがあったり、僕だって毎回見ていて胃が痛くなったりするくらいのほうが面白いと思う。だから今の稽古も2日ぐらい作品のおさらいをしたら、次の稽古では作品とは直接関係ない別のことをやったりして、インプットとアウトプットが極力固まっていかないようにしています」
それは上演の鮮度を保つということを超えて、普遍性に回収されない個人的事実を見つめようとする、本作の基本姿勢とも関係するのだろう。初演のパンフレットで彼は、個人史の可能性が、「記憶装置としての身体が、いままさに誰かに『語り出そうとする』その現在形の身体にあるのではないか」と問いかけている。
稽古に取り組む出演者の間からは、「ムツカシイ」、「ムツカシイね」と言い合う声が折りにふれ聞かれる。全体像は、自分たちの演技と切り離された"物語"として理解されるものではない。また具体的な指示も、精緻化と流動化という二つの方向性を含んでいる。それでも一つ一つの指示を咀嚼しようと、「これでいいの?」、「このほうがいいのんとちがう?」と確かめながら進んでゆく。
「今度の稽古では、私達もついてゆくというか、食らいついてゆく姿勢ができたと思います。最初は言われても『あ、そうするの? そうなの?』ぐらいのことだった。でもやっぱり初演があり、他の演劇を見せてもらったり、色々な指示が「なぜそうなのか」と細かく教えてもらったりする中で、ある程度受け入れ態勢が出来て、ついていけるのかな」(三木)
「参加させてもらって、演劇の見方みたいなものが変わって来たわね。でも、この年寄りをちゃんとしてくれはったいうのがなあ。彼もしんどかった思うよ」(中川)
確かに、ここに至る道のりを想像すると、ちょっと言葉がない。出発点で両者の間には、年齢差以上に、ともに取り組む課題、つまり"演劇"の捉え方において底知れぬギャップが横たわっていた。
「最初の頃、『僕の作品を見てください』って言われて、彼の映像を見たときの衝撃はすごかったです。『えっ、こういう世界にわたし入って行くの?』ってね。『どう感じられましたか』と聞かれても、シーンとなって誰も返事をしなかった。できなかった。だからそういうところに入って、1年2年の間に通じ合えるものができたことに、私は感動している」(三木)
「今は演出の相模さんやらのおっしゃることに興味があって、来ています。完全にではないと思うけど、だんだん意味が理解できるようになってきました。それまでは、面白くないといったら失礼だけど、『これやってて何の意味があるのか』とすごく考えた。」(足立みち子)
初演の舞台に立ち、さらに今、体力的な不安をおしてフェスティバル/トーキョーに臨むのは、このようなミスコミュニケーションをも含む相互関係を経て、つながっているメンバーだ。初演後にその経緯を、『わたしたちは夕日を見るードラマソロジーの顛末ー』にまとめ、自費出版までした三木は、その"ご縁"を作品を見てくれた人の中にも見つけて言う。
「言葉とか体で表現する芸術のジャンルというものは、どこかでつながっている。私は全然そういう体験がないから、目を白黒させて、みんなに『70過ぎて初体験てあるのよ』って宣伝している。70歳を過ぎて、これまで生きてきたことが180度覆されるような体験ができたのは本当に貴重だった。再演と聞いて、これはいい加減じゃいけないわって」(三木)

ここでは、巧と名のある芸術家が市民を導くのとはまた違ったことが、いや、そういった関係においては不可能なことが起こっているように思われる。両者の関係を象徴する一つが、参加者たちの戦時中の記憶/体験の扱いをめぐるやりとりだ。実はエルダー世代は応募にあたり、この点についてかなり明確な意志を持っていた。70歳以上に年齢を絞って「あなたの話を聞かせてください」という募集の仕方も関係して、彼らは後世に伝えたいという切迫感、そのために来たのだという使命感を隠さない。
「我々は引揚者でしょ。収容所に入れられたり、本当に辛い思いしましたよ。でもそんなこと言ったりしても通用しないでしょう。若い人にはねえ」(藤井)
「でもこの世代でないとわからないですよね。単なる"歴史"としてしか知らない。我々は実際に体験しているから相通じるものがあるわけですよ」(飯田)
ところが、この要望に対して相模は逆説的な手段をとる。例えばテクストにおいて、歴史と倫理に触れるこのサブジェクトは、個人の生の一要素として、日常に埋め込まれた「〜が好き」や「〜がしたい」と等価に扱われることになる。それはエルダー世代には、にわかには理解しがたいことだった。
「子孫に伝えようと思って来ているのに、相模さんはそこは重心じゃないと言う。そのあたりはねえ。納得? う〜ん。でも確かに、そういう話を娘にふだんしようとすると、なんか嫌がられるわねえ。『よそのお母さんはそんなこと言えへんよ、忘れて今にマッチして生きてるよ』って言われる」(相馬)
相模としては、それはエルダー世代の語りがいかに舞台にのるか、どうしたら聞こえてくるか思案した上での策だった。とりわけ戦争体験を語り聞かせるという課題が孕むジレンマを、稽古を始めて数ヶ月後に関係者を前にして行った試演会で受けとめたからだ。
「みなさんが舞台上にいて、語る姿っていうのが僕にもわかんなくて。好きにしゃべってもらったら面白いのかなあと思って、そうしてもらったんです。そしたら案の定、『聞けないなあ』って感じだった。『この届かなさってなんだろう』ってところから、舞台上で語られる言葉を客として聞く、世代を超えた客に聞かせるにはどうしたらいいのかなあって。しかもプロの俳優でもない人の言葉を、極力僕が制限してしまわないかたちで届かせる仕掛けがいるなあってことで、いろいろ試し始めた。それがああいうかたちになった。」(相模)
その「いろいろ」は、素人の体を舞台に上げる手続きや、彼らの見え方聞こえ方を決める映像・舞台芸術の技術を駆使した配慮に認められる。出演者たちには、「自分自身のことを個として語る」という課題が突きつけられた。相模が最低限貫こうとしたこの要求は、戦争という特殊な体験において強く結びついた「私達」の主体のあり方の核心を突くとともに、記憶装置としての彼らの存在をまるごとフィーチャーする本作の軸をなすことになる。
『ドラマソロジー』はこのように、最も隔てられているかのように見える芸術家と市民が、互いに妥協できない部分で交換し合った成果とも捉えられる。そこでの収穫は、作品の芸術的革新性にとどまらず、制作の途上でダイナミックに再編され、上演によりさらに拡張してゆくコミュニティでもある。その種蒔きをしたアイホールのディレクター、小倉は「地域とつくる舞台シリーズ」について次のように語っている。
「この企画で一緒に組むアーティストは、これまでのアイホールが培ってきた価値観のなかで、選んでいきたいと思っています。地域の方々を巻き込むこのような企画でも、ワークショップやコミュニケーションの上手な人を呼んで来て単純に分かりやすくして伝えるのではなく、あくまでこれまでのアイホールのやってきたことを変えずに、みなさんに伝えたいです。ゆっくりじっくりと少しずつ、それは伝わると思います」
(敬称略)

DRAMATHOLOGY / ドラマソロジー
構成・演出:相模友士郎
出演:増田美佳、足立一子、足立みち子、飯田茂昭、相馬佐紀子、中川美代子、藤井君子、三木幸子
公演スケジュール:2010年11月26日(金)-11月28日(日)
会場:東京芸術劇場小ホール1


